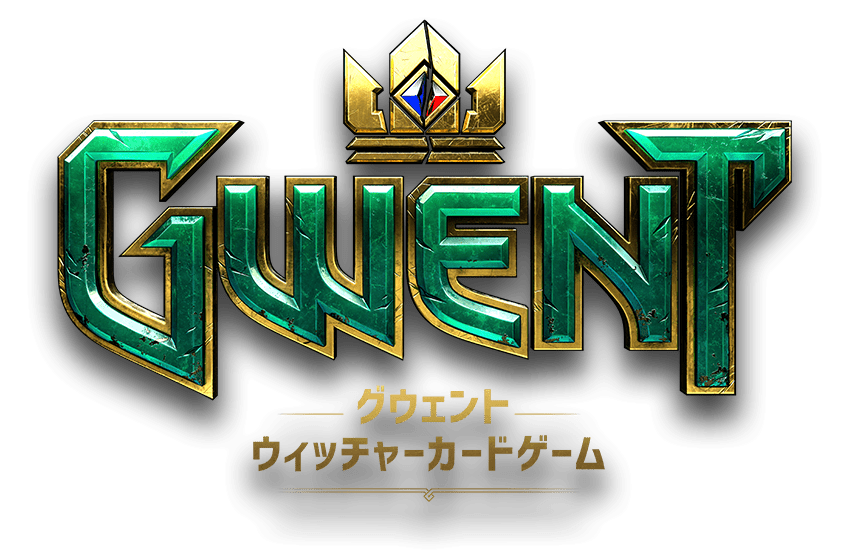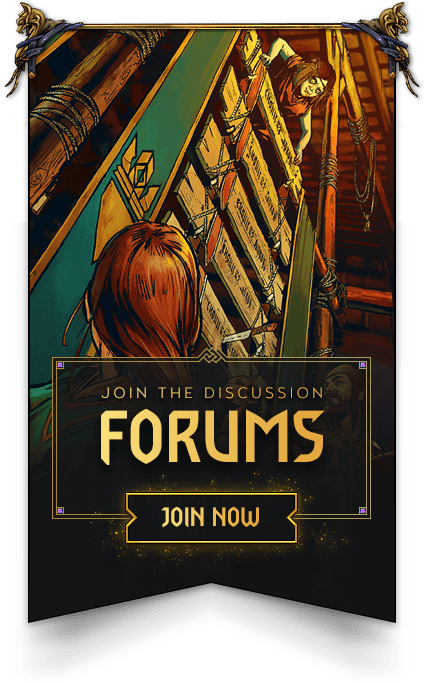ダンディリオン
ダンディリオンは戦いのさなかにあった。
摂取したアルコールが血管内で脈動し、彼の感覚を鈍らせる。頭の奥のほうにズキズキと痛みが走った。ぶり返す鈍痛の波に合わせて、激しく息が吐き出される。
吟遊詩人は息も絶え絶えに罵り声をあげた。この吐き気は胃の中のウォッカを強制的に排出しなければ収まりそうもない。抵抗も虚しく、彼はシーツを濡らし、再び怒りに満ちた声をあげた。そしてゆっくりとベッドから一歩踏み出す。さらにもう一歩… 足はいうことを聞かず震え、見るからにぐらついていた。そして喉の渇きが彼を苦しめた。
水差しに手を伸ばしながら、昨夜の記憶を辿ろうとした。
春の祭り――長い歴史を持ち、エルフの文化が流用されたものであろうそれは、小さなガレットの町に大勢の人間を呼び寄せる。大量の酒と食べ物が振る舞われる大仰な祝祭だが、洗練された娯楽が欠けていた。そこで町長は、若き詩人の才能を買い、その需要を満たそうとしたのだ…
報酬が少なすぎる――水差しの縁に残った最後の一滴を舐め取りながら、ダンディリオンは思った。
どう考えても割に合わない。
ゲラルト
ゲラルトは戦いのさなかにあった。
飲み込んだ霊薬は未だに血管内を駆け巡り、感覚を研ぎ澄ませる。夜の湿った空気が肺に張り付いていた。繰り出す攻撃に合わせて、激しく息が吐き出される。
なんとか鱗に覆われた化け物の肉を断ち切ろうと、ウィッチャーは大きく罵り声をあげた。その斬撃がついに相手を捉える。だが手負いの怪物はすぐさま水中に潜り、その巨体を隠した。ゲラルトは息を切らし、再び怒りに満ちた声をあげる。そして慎重に、一歩前へと踏み出す。さらにもう一歩… 分厚い泥がその足に纏わりつく。その時、ぬめりとした何かがブーツに入り込み、骨の芯まで寒気が走った。
振り返るのとほぼ同時に、黒い水面がしぶきをあげる。
姿を現したのは、この沼と同じだけの齢を重ねているだろう巨大なヴァイパーだ。長年に渡り、ガレット周辺で獲物を捕食し、殺戮を繰り返し成長し続けるその体は肥え、硬い鱗に覆われている。だがそれもここまでだ。この怪物に対し、町長はウィッチャーに討伐依頼を出したのだ…
報酬が少なすぎる――放たれる猛毒をかわしながら、ゲラルトは思った。
どう考えても割に合わない。
ダンディリオン
おぞましい光景を目にした町長の娘は、嫌悪感から思わずたじろいだ。それでも彼女は、父の客人がいる部屋の奥へと足を進めた。そしてベッドの傍らで足を止めると、ダンディリオンに意味ありげな視線を投げかけた。
こうした粗相を見られた後は、決まって軽蔑の視線を向けられるものだ。そんなことには彼も慣れっこだった。だがそれでもなお、彼は魅惑的な笑顔を浮かべた。実際のところ、ダンディリオンほどの笑顔を作れる者はそうはいない。
しかし町長の娘は、諦めと共に溜め息をついた。
それどころか、彼女はダンディリオンを驚かせるほどの冷淡さを見せ、単刀直入に春の祭りにおける彼の出番について切り出した。彼女曰く、詩と歌があってこその祭りであり、それらが欠けることは許されず、彼の若さや、彼女の控えめな表現で言うところの“疑問の余地の残る”その才能は、なんら失敗の言い訳になるものではないという。
ダンディリオンはそんな彼女の控えめな胸を見つめ、それを題材にした悪意に満ちたバラッドを考え始めていた。
彼は再び満面の笑みを浮かべた。
ゲラルト
おぞましい戦果を目にした町長は、嫌悪感から思わずたじろいだ。それでも好奇心から、巨大な口を覗き込むと、ヴァイパーの歯を数えだした。その数が30を超えた辺りで諦め、ゲラルトに意味ありげな視線を投げかけた。
ウィッチャーは肩をすくめた。町長のような立場にいる役人は、得てして賞金の支払いを渋る口実を探すものだ。だが、ヴァイパーの頭を机に置かれてしまっては、戦果に対して物言いをつけるのも難しいだろう。
故に、ガレットの町長は約束通り賞金を支払った。
しかも珍しいことに、彼はウィッチャーを歓迎し春の祭りへと誘ってきた。通りではたっぷりの酒と肉が振る舞われ、若いながらも卓越した才能をみせる詩人の催しも予定されているという。「どうか羽を伸ばして、祭りを楽しんでください」町長からもそう強く勧められた。
ゲラルトは部屋を悪臭で満たし始めていた血まみれの頭を見つめた。
そしてもう一度、肩をすくめてみせた。
ダンディリオン
市場まで足を運んだダンディリオンは、これから始まる余興のために用意された舞台に直行した。遅刻の埋め合わせにと、まずはリュートの弦をつま弾いて演奏を始めた。店番をしていたすんぐりとした体格の女の横を通り抜けたが、詩人の溢れ出る才気にもかかららず、彼女はほとんど関心を示さなかった。
だが舞台周辺の聴衆は違っていた。
彼らは興奮した様子でひそひそと何事かを話しだし、道をあけていく。ウィッチャーと思われる白髪の男さえもが同じようにしてくれる。なんと! ガレットの人々は、演奏を聞かずとも天才を認めることができるのだ! なんて素晴らしい町だ! ダンディリオンは深々と礼をして、帽子に着けた鷺の羽根で石畳を撫でた。
そして彼は、聴衆の静かなる期待を満たす。
その指がリュートの弦を素早く弾いた。その足取りと旋律はつめかけた観客全てを魅了した。しかし真に人々の心を射抜いたのは、その魅惑的な歌声だった。演奏を終えた時、偉業を成し遂げたという確かな手応えを感じた。
先ほどのウィッチャーさえも、彼の詩に心を打たれ、涙を浮かべながら立ち尽くしていた。
ゲラルト
市場まで足を運んだゲラルトは、すぐに舞台に向かおうとはしなかった。まずは自分自身の愉しみを確実なものとするため、必需品を調達した。つまり、ウォッカの瓶とソーセージだ。店番をしていたずんぐりとした体格の女は、彼にさして注意を払わなかった。
だがその店番はあくまでも例外だった。
周りの聴衆はひそひそと何事かを話しだし、道をあけていく。白髪のウィッチャーを目にして恐怖を隠しきれない者もいれば、あからさまに視線を投げかける者もいた。ゲラルトはそうした反応を全て無視しながら、落ち着いた様子でウォッカを飲み、脂っこいソーセージを味わった。
やがてそこにリュートの音色が響き、聴衆の関心はゲラルトから離れていった。
音楽は近くの町役場から聞こえてきたが、演奏者の足取りと旋律は乱れ、二日酔いの状態なのは明らかだった。しかしひとたび彼が歌いだすと、その声は実に心地よく、「二つの小さな乳房が奏でるバラッド」と題された歌は、粗削りではあったものの、なかなかどうして愉快なものだった。とはいえ、演奏が終わってみると、ゲラルトは美食の味わいは芸術のそれに勝ると結論付けた。
ウォッカの最後の一口が喉を焼き、彼の目には涙が浮かんだ。
ダンディリオン
音楽は官能的刺激を与える。それは紛れもない事実だ。吟遊詩人の韻は見事で、その歌は確かな技術に支えられ、女性的な輪郭をものにする術も持ち合わせていた――それは即ち、彼がひどく魅力的であるということだ。女たちはその体を見せたがり、おかげで場の雰囲気は、ウォッカでも作り出せないほどの高揚感で満ちていた。
祭りの輪に加わるわけではなかったが、ダンディリオンはその場に留まり、特に熱をあげていたガレット住民の女性と時間を共にした。すぐに彼は喜びを感じた。今朝からずっと欲していた喜びだ。
だが突如として怒号が響き渡り、彼の期待は即座に霧散した。
そのとき吟遊詩人は、舞台の下で横たわっていた。女がかぶさった状態で、“剣”を抜いている。武器を持った襲撃者たちが彼の隠れ場に入り込んできたが、幸いにも、それまでに彼の剣は鞘に収まっていた。武器を手に襲い掛かってくる彼らを前にしても、愛する人を守るべく、吟遊詩人は決してひるまなかった。いかにも華奢なその風貌から、彼を取り囲んだ悪党たちは見るからに油断していた。これならいくらでも隙を突けるはずだ。さらに、先ほど見かけたウィッチャーが詩人に加勢した。それほどまでに彼の演奏を気に入ったということだろう。2人の英雄と、名もなきごろつきたち。
ダンディリオンは勝算ありと睨んだ。
ゲラルト
音楽は猛獣でさえもなだめる。それは紛れもない事実だ。ゲラルトに対して険悪な視線を向けていた聴衆も、今ではウィッチャーと共にウォッカを飲み、ソーセージを口にしている。そして陽気な音楽と踊りが皆の気分をさらに高揚させた。誰の心にも同じ思いが浮かんだ――彼は善人に違いないと。
祭りの輪にほとんど加わることはなかったが、ゲラルトはその場に留まり、ガレットの人々が賑やかに行き交う様子を眺めた。その光景に彼は至福を感じた。もう長いこと感じてこなかった喜びだ。
だがそこに悲鳴が響き渡り、幸せは長くは続かなかった。
舞台の下で乱闘騒ぎが起きていることをウィッチャーはすぐに察した。剣を片手にそちらへ駆け付けたが、すぐに刃を鞘に収める。襲撃者は武器を持っていなかったのだ。ようやく昨夜の酔いから解放されたと見える先ほどの若き吟遊詩人を、彼らは取り押さえていた。そして荒々しく詩人を揺さぶると、そのまま殴り掛かる姿勢をとった。その後ろで、半裸の女が金切り声をあげ、どうにか襲撃者と怯える詩人の間に割って入ろうとしていた。これは簡単な数の問題だ。4人の荒くれ者が、縮みあがっている1人の男を取り囲み、その者は明らかに身を守る手段を持ち合わせていない。
ゲラルトはその偏りを均すことにした。
ダンディリオン
事態が落ち着くと、ダンディリオンは救い出された女に口づけをしてその場を立ち去り、何食わぬ顔で沸き立つ群衆に紛れ込んだ。ウィッチャーに別れを告げようとはしなかった。男同士、こういった状況で言葉を交わす必要はない。ところがしばらくして、そのウィッチャーが後をつけてきていることに気付くと、ダンディリオンはおもむろに振り返り、背後の男に向かって手を差し出した。
ウィッチャーはその仕草を見て、ぎこちなく彼の手のひらではなく袖を握りしめた。詩人のあまりの魅惑に呆然としたのだろう。うまく言葉は出てこないが、話をしたがっているのは明らかだ。ややあって落ち着きを取り戻すと、ウィッチャーは思い出したかのように、“リヴィアのゲラルト”と名乗った。そしてさらに、はっきりとそう言ったわけではないが、連れ立つ相手を欲しているのも明らかだった。ウィッチャーの日常はあまりにも孤独で、話しかける相手も愛馬くらいしかいないのだろう。ひとまずダンディリオンは、もう少し静かなところに場所を移すことを提案した――豪勢な調理場を備えた、名のある売春宿だ。無論、これはその場に向かうためのこじつけのように聞こえるだろう。だがその実は、詩人の良心に基づく行動だった。
そうして2人の旅が始まる。
吟遊詩人とウィッチャーの旅が。
ゲラルト
襲撃者たちが倒れ、女が服をまとった段階で、ゲラルトは異変に気づく。詩人の姿がない。どうも妙だ。“高潔なる文化の伝道師”はなぜそこまで焦って逃げ出したのか。彼自身に何か負い目があるのだとしたら? たとえばこの状況を根底から覆すような何かを彼が隠しているのだとしたら? 幸いにも、彼はそう遠くまでは逃げていなかった。まだ舞台周辺の群衆に紛れていることにゲラルトは気づく。そして先ほどの襲撃者たちがしたように、詩人の色鮮やかな服に掴みかかった。若き詩人は初めこそ怯えた様子を見せたが、すぐに我に返る。そして鷺の羽根がついた帽子を手で押さえながら丁寧にお辞儀をし、ダンディリオンと名乗った。この事態は単純な誤解から生じたもので、もう少し落ち着いて話せる場所でなら、喜んでどんな質問にでも答えることを約束した。実のところ、彼は最適な場所を知っていた。売春宿だ。彼は持ち物のほとんどを昨夜そこに置き忘れていた。舞台のほうからは怒号が聞こえ、徐々に相手が近づいてきているのが分かった。明らかに詩人は助けを必要としている。
そうして2人の旅が始まる。
吟遊詩人とウィッチャーの旅が。
ダンディリオン
〈小さな花〉に到着したダンディリオンは、ひとつの結論を導き出した。あの襲撃者たちは、嫉妬に駆られた同業者の刺客に違いない。彼は記憶を奥深くまでたどり、とあるシダリスの男を思い浮かべていた。奴だ。奴はこの俺の才能を、明らかに妬んでいた。才能の欠片もない臆病者め! 悪漢を雇い、自分より優れた詩人を殺させようなど、なんと哀れな真似を…! 屈辱を感じたダンディリオンには、このまま見過ごすことなどできなかった。今すぐにでもここを出て、正義の裁きを下さねば。
だが、復讐はまだ為されていない。彼にはウィッチャーの相手をする役目があった。
ゲラルトは無礼さにも構わず、ふくよかな胸の女主人に夢中になっている。ダンディリオンはふと、この変異者が最後に欲望を満たしたのはいつなのだろう… と考えかけたが、それ以上はやめておくことにした。今この時を最大限に楽しもう。給仕係の女に声をかけ、店の名物である地元料理を注文し、新しくできた友人のために最高級のウォッカも気前よく振る舞った。その見返りに、もう少し心を開いて饒舌になってくれるといいのだが――と願いながら。
だが残念ながら――
そうはならなかった。
とは言え、時を経るにつれゲラルトを愉快な男に感じ始めていたのも事実だ。酒が入ればなおさらだ。話し込むうちに、ダンディリオンは彼の本名さえ聞き出すことに成功した。その名は確か… ゲラルト・ロジャー・エリック・ドゥ・オー・ベレガルシー。
一字一句、間違いない。
ゲラルト
〈小さな花〉のたくましい女主人は事情をよく知っていた。だがゲラルトはさして驚きもしない。この手の場所では、不快さを伴う噂話はすぐに広まるものだ。女主人の話によれば、ダンディリオンが最近関係を持ったという娘には、過保護で知られる兄が4人いるらしい。さらに厄介なことに、彼女は裕福かつ極めて不快な商人と婚約していた。商人の家族が求めてやまない結婚を、彼女が約束していたのである。決まりだな――とゲラルトは見切りをつけた。奴との旅もここまでだ。これで後ろ暗い思いもなく別れられる。
しかし当のダンディリオンは呑気な様子で、自分の置かれた状況にまるで気づいていなかった。詩人は白昼夢からはたと目覚めたかのように、タマネギ入りのグロート2人前と、粗悪だが度数の強い密造酒を1瓶注文した。「一番安いのにしてくれ」と彼は囁き、財布に残っていた最後の硬化を投げる。食事と、そして何より酒を振る舞ってくれたことにゲラルトは感謝しつつも、食べている間は口を閉じてくれと願った。
だが残念ながら――
そうはならなかった。
とは言え、時を経るにつれ彼の無駄話にさほど苛立ちを覚えなくなったのも事実だ。酒が入ればそれはなおさらだ。ウィッチャーは、ヴィカヴァロの乙女についての歌を詩人から教わりさえした… いや、ヴィカヴォロだっただろうか?
まあそのような名前だ。
ダンディリオン
2人は手を取られ、壁に背中を押し付けられる。非常に心地のよい経験だったが、娼婦たちは突然いなくなり、彼らは暗闇に取り残された。
ダンディリオンは闇が薄れ、奇妙に傾く床が止まるのを待った。女は残酷な仕打ちをするものだ。まさかこんな風に放っておかれるとは。あれだけ親密に寄り添い、笑い合ったというのにか? 彼は確信していた。これはきっと、受けてもいない接待費を請求されるぞ… だがまあ、少なくとも酒はある。
ダンディリオンはボトルを持ち上げた。それはまるで、自ら彼の手に飛び込んできたようだった。一方ゲラルトは、何事かをぼそぼそと呟いている。叫び声がどうしたとか、そのワインの代金を払えだとか。どんな状況でもやたらと問題を見つけたがるのは、ある種の職業病かもしれない。さて、何の話だったか…? しかしそんなことはどうでもいい。ダンディリオンにとって、他愛ない話は時間の無駄でしかなかったのだ。彼は言葉を操るだけではない、行動派の詩人だ。だからゲラルトに対し、さっさと何か役に立つことをしろと命じた。ここから出る方法を考えるか、せめて酒を飲もうじゃないか、と。しかしこの堅物は、さらに文句を言い始めた。ウィッチャーがこれほど道徳にうるさい良心的存在だったとは、一体誰が信じるだろう?
彼と議論するつもりはなかった。自分の行動の道徳的相対性を議論し合うには、明らかに酒が足りていなかったのだ。だから彼は諦め、〈小さな花〉に対する多額の支払いを手配した。
ゲラルト
正面の扉から兄弟の2人が勢いよく現れた。残り2人の兄弟も、裏からそっと入っている。もはや安全な場所は地下室しか残されていない。近くにいた娼婦の助けを借りながら、ウィッチャーと詩人は素早く姿をくらまし、兄弟たちを出し抜いた。
ゲラルトたちの頭上で、4人の足音が響く。売春宿を探し回る兄弟たちの苛立った声が地下室にまで届いていた。ゲラルトは戦闘を避けたいと考えており、一方のダンディリオンは… ダンディリオンは、ワイン棚を夢中になって物色していた。
助けてもらったのに盗みを働くなど、道義に反する。思わずそう指摘したゲラルトに対し、ダンディリオンは怒りをあらわにぶつぶつと反論をした。盗んでるんじゃない、今は代金を払えないだけだ! と。彼はワインボトルを置き、バッグから筆記具を取り出し、手紙をしたため始めた。ゲラルトはその様子を静かに見守った。それはガレット町長にワイン代を請求する内容だった。出演料の最後の支払いをまだ受け取っていない。彼はそう主張したのだ。しかし今受け取りに行くことはできないのだから、 目の前のワインに使うのが良いだろう、と。
ウィッチャーは反論することができなかった。それは彼自身が集中力をなくしていたからだ。そして合意のもと、彼は棚のボトルを1本取った。
ダンディリオン
ハッ! とダンディリオンは声をあげる。暗闇の中に、ほのかな光を見たのだ。だが待て… そもそもここはどこだ? まあどこだろうと構わない。ウィッチャーは脱出について熱弁を振るっているが、重要なことを忘れている――ワインだ。酒が足りない。
だが、あの光は出口なんだろう? しかしずいぶんと高いところにあるし、階段もない… しかも扉の代わりに格子がついているのか? あれはいったい… な、なんだ!? 詩人は自分の頭を押さえた。突然の衝撃に彼の体は吹き飛ばされ、さらに悪いことに、酔いが少し醒めてしまった。数秒を経て、天井と床が再び入れ替わる。誰かが… おそらくゲラルトが… 詩人を小麦袋のように投げ飛ばした。いて! と彼はうなり、硬い石の上に着地する。そして視線を下げると… ああ! ダブレットに入れたワインボトルが残っていた。無事だったのだ! なんたる英雄的行為! これは素晴らしいバラッドの題材になる。詩人はそう確信した。なぜならば、それを自分で書くつもりだからだ。シダリスの愚か者についても、こき下ろしてやろう! ハハハ!
ところがその考えを話すと、ゲラルトは勢いよく笑い出した。ダンディリオンは耳を疑った。命に関わるほどの事態だというのに、この男はヒイヒイと声をもらし、まるで処女を奪われた娘のよう… いや、待てよ。と、そこで詩人は悟る。彼は昼間に舞台上でうたった歌を口ずさんでみた。いや、待て。舞台の下か…? そしてウィッチャーに告げる。一緒に歌ってくれ! 思い出す助けになるかもしれない…
まさか、嘘だろ!? そんな… 信じられない! ゲラルトめ、よくもそんなことを!? なんと無礼な… ワインを分けてやったというのに。秘密を打ち明けてやったというのに。兄弟のように愛してさえいるんだぞ!
ゲラルト
シーッ、とダンディリオンが囁く。上にいる奴らは… いや、待てよ。上にいるのは誰だ? ゲラルトは思い出すことができない――が、まあいいかと諦めた。
連中はもういない。そうだろ? だが危険を冒す必要もない。地下室には人が十分通れる大きさの窓があったのだ。格子で塞がれてはいたが、アードを使えば問題はない。だが慎重に… 静かに… くそ! どうなってる!? ゲラルトは眩暈を振りどくように頭を振った。一方ダンディリオンは、揺れる床の上で起きあがろうともがき、足を絡ませ転げている。
窓は消え、窓があった場所には大きな穴があいていた。
ゲラルトは暗い通りに出て振り返り、破壊された〈小さな花〉の壁を見た。待て。どうして俺はここに…? ウィッチャーは自問した。ダンディリオンの仕業かもしれない。この間抜けは何かと… おや、ダンディリオンの奴め、ワインを持ってるじゃないか。こいつは最高だ。
ゲラルトはワインを受け取り、一口飲んだ。そして詩人の長話に耳を傾けた。奴が一番の何だって? シダリスのどの吟遊詩人だって? ああ、ダンディリオン、この間抜けめ。こいつはとんでもなく鈍い奴だ。これは他の吟遊詩人の策略なんかじゃない。悪ふざけがもたらした、ただただ不快な結果だ。
ウィッチャーの頭の中で再び時間が飛んだ。これで3回目だ。いったい何の話をしていただろうか? やかましい詩人のせいで、ゲラルトは集中することができなかった。おい! そろそろ耳を休ませてくれ! それからワインもだ! 酒が足りない!
大丈夫だ、とゲラルトは手を振る。心配するな、お前のことは尊敬してる。ああ! 俺だって兄弟みたいに愛してるさ!
ダンディリオン
ダンディリオンがベッドで目を覚ますと、隣には美しい女性が眠っていた。これ自体は喜ぶべき展開だが、異様に頭が痛むのが気がかりだった。夜中に一緒に酒を飲んでいたウィッチャーの友人との記憶も曖昧だ。その上、部屋に散らばる自分の持ち物の中にリュートがなかった。必死に探し回っている間、女性の大きな緑色の目がこちらを射抜くように見つめている。まるで、何かを非常に… 楽しんでいるような目つきだ。
不意にゲラルトと交わした重要な会話を思い出し、ダンディリオンは顔をしかめた。ウィッチャーは彼に、なぜ悪漢どもに追われているのかを大雑把に説明し、2人は一刻も早く街を出たほうがいいという結論に至ったのだった。しかし、今の状況はどうだ。ガレットの門を潜ることなく、町長の家の一室で、緑色の瞳の娘とともにいる。よくよく見ると、どこかで会ったことがあるような気がする… おそらく彼女の視線のせいだ。気づけば背筋が凍るような、妙な笑みを浮かべているではないか。
他にどうしようもなくなったダンディリオンは、リュートの行方と、なぜ彼女がこちらを見て笑っているのか問いかけることにした。
ゲラルト
ゲラルトは、厩舎の泥の中でローチに見守られながら目を覚ましたことに驚いた。それ自体は決して珍しい状況ではなかったが、今回はまるで毒物への耐性を失ったかのような不快な気分だった。昨晩の出来事の記憶はぼんやりとしていて思い出すのも一苦労だが、それよりもダンディリオンのリュートを小脇に抱えて寝ていたことの方が問題だった。ウィッチャーがそれをじっくり調べようとすると、ローチが妙に人間のような、まるでゲラルトを咎めるような表情を浮かべた。酔っ払って遅くに帰ったこと、それから…
昨晩のダンディリオンとの豪遊ぶりを思い出し、ゲラルドは顔をしかめた。中でも馬鹿げた会話をしていた記憶が蘇った。詩人は4人の怒った兄弟の話題から巧みに兄弟愛の話題へと持ち込んだ。にも関わらず、お互いに背中を叩きあいながら儚い恋よりも男の友情を讃えているうちに、2人で街を出ようということになっていた。しかしその計画が実行されることはなかった。何か不運な出来事が起きたせいだ… ウィッチャーは記憶が蘇れば蘇るほど、早くガレットから去りたくなってきた。ローチもこちらを見つめているばかりでなく、責めるように鼻を鳴らし始めている。
深い溜め息をつきながらゲラルトは重い体を起こし、鞍に付けられた鞄にリュートを隠した。息をするように美しい嘘を紡ぎ、運に見放され、子供じみた吟遊詩人を探しにいかなければならない。
ダンディリオン
結婚式。
結婚式が執り行われることを、新郎すなわちダンディリオンは先程花嫁から聞いたばかりだ。彼女の名がコーラであることも今更になって知った。結婚するにあたって最低限の情報ともいえる…
詩人は心の中でコーラ、と彼女の名前を繰り返した。ひとまず、そこそこ美人じゃないかと自分を慰めた。だがこのままでは結婚という枷に生涯捕らわれることになる。更に悪いことに、結婚式は祭の2日目である今日行われるらしい。この日は皆で婚礼を祝う、盛大な宴なのだそうだ。コーラは本来ならば別の男と結ばれるはずだったのだが、どんな大商人といえども貴族には敵わない。レッテンホーヴ子爵ジュリアン・アルフレッド・パンクラッツ、通称ダンディリオンはため息をついた。いつ彼女に爵位を明かしたのかも思い出せないどころか、プロポーズをした覚えもないのだ。こちらに関しては、実際していないのだろう。コーラの以前のフィアンセは、おそらく商品である魚の臭いが染み付いた嫌らしい年上の男なのだろう。身内だけでなく、町民を巻き込んでの結婚式を選ぶようなケチくさい男だ。若い娘がより自分にふさわしい相手を選びたくなるのも当然だ。欲深い老いぼれよりも、貴族と結ばれた方が両親も喜ぶ。そうすれば兄弟たちもようやく落ち着き、新たな伴侶は自分の邪魔をせず、礼儀正しく、静かにしていてくれる。
これぞ理想の結婚だ。
ゲラルト
葬儀。
市場で喜ばしい知らせを聞いたゲラルトは、必ず葬儀が行われるだろうと確信した。すでに、コーラという若い女性とレッテンホーヴ子爵の不釣り合いな婚約の噂が広まっていたのだった…
もしや、夜中に恥をかかされたとダンディリオンを怒鳴りつけていた女性のことだろうか? 怒号を浴びせられた本人は、必ず報いるからと都合のいい嘘をつき始めた。それでも彼女の気がすまないと見ると、爵位をちらつかせたのだった。おそらく、それも嘘だろう。しかしコーラはそれを聞くなり機嫌を直し、なんとか兄弟や街の衛兵を呼ばれずに済んだのだ。大した脅威ではなかったが、すっかり酔っ払って判断力の鈍っている状態では侮れない相手だ。そういうわけでダンディリオンはウィッチャーにリュートを預け、コーラが眠りについたら戻るからと、彼女についていくことになったのだった。ゲラルトは、おそらく彼女がベッドを抜け出し、商人や他の者たちに結婚の話を言いふらしたのだろうと考えた。彼女の家族は今頃、中断していた祝宴の準備を再開しているだろう。相手の男が裕福な商人などではなく、単に貧乏な芸術家であることにはまだ気づいていない。しかし、新郎の正体はいずれ暴かれる。花嫁の兄弟はタールを火にかけ、新郎になるはずだった男を処刑人のところに連れて行く。
簡単な葬儀で済むだろう。
ダンディリオン
ダンディリオンは婚約の噂がまだ広まっていないことを祈っていた。大した話題になっていなければ、婚約を破棄するのも簡単だ。しかし部屋を出ようと扉を開くなり現れたガレットの町長に若き2人の門出を祝われ、あっという間に吟遊詩人の希望は潰えた。通りすがる召使いたちは、2人の身支度を手伝いながらにやけ顔を隠しきれないでいるようだった。しかし外に出てみると、コーラの4人の兄弟たちが見せつけるように拳を鳴らしながら待ち受けているではないか。兄弟らは、子爵が約束通り家族の一員となるのであれば、豚肉に卵と小麦粉をまとわせる要領で彼にタールと羽根をぶちまけないと申し出てくれた。さらに、一家が新たに住むことになる城の警備も任せてほしいと。どうやら子爵は城を持っているものだと思い込んでいるようだ。ダンディリオンは唾を飲んだ。城なんてどこで手に入れろと言うんだ。実際のところ、こんな連中の期待はどうでもいい。面倒なことになる前にさっさと去ればいいだけの話だ。だが最大の問題は、リュートがどこにも見当たらないことだ!
町長が、テーブルの上には所狭しと並べられたご馳走を前に誇らしげにしている。その周りには絶えずバイオリンをかき鳴らす二流の音楽家たちが陣取っている。テーブルの片端には、花とツタで作られた婚礼用のアーチが建てられている。ここで各人が宣誓を行うのだ。アーチの向こうには、結婚を祝う踊りが行われる市場の中央広場が見える。
役人の言葉に耳を傾けようと、ダンディリオンは背筋を伸ばした。
まもなく自分たちの順番が回ってくる。
ゲラルト
ゲラルトとしては詩人を逃がし、葬儀が行われるような事態を避けたいところだった。ダンディリオンのことだ、婚礼の儀から逃げようとするのも時間の問題だろう。ウィッチャーは二日酔いの詩人とその花嫁に会うべく町長の家に赴いた。しかし、邸宅の門に着くなり彼は見知った顔に迎えられる。町長自らが結婚式の参列者を率いていたのだ。どうやら若い娘は兄たちまでなだめたらしい。何と言って説得したのか、ゲラルトは考えたくもなかった… 何せこれ以上深入りする謂れもないのだ。共に一晩飲み明かしたからといって詩人を救う義理はない。酩酊した状態で交わした約束を守る必要もない。そう自分に言い聞かせ、ウィッチャーは厩舎に向かおうとしたが、荷物の中に詩人のリュートがあることを思い出してしまった。深い溜め息をつきながら、ゲラルトは踵を返した。
ウィッチャーは、捕まる危険を冒してまでダンディリオンのために騒ぎを起こす気はなかった。しかし、しばらくここに留まって手を貸す機会を伺うくらいはいいだろう。
だが花嫁とその兄弟がダンディリオンのそばを離れることはなかった。町長はというと、気の利く主催者の役割を買って出て、招待客に祭や地元の儀式について説明して回り、緊張感溢れる状況には気づいていないようだった。
ゲラルトは一行から少し離れて歩き、聞き耳を立てながら詩人が動き出すタイミングを見計らっていた。
ダンディリオン
ダンディリオンは踊った。
力の限りに踊った。ガレットの伝統に従い、花婿は舞い踊る群衆の中へ飛び込み、花嫁を救い出さなければならないのだ。そうして初めて、結婚式は本当の始まりを迎えるのである。即ちこの吟遊詩人にとっては、窮地を脱する絶好の機会というわけだ。しかし不運なことに、将来の義兄弟たちもまた同じ発想を持ち合わせていた。彼らは先回りして逃げ道をふさぎ、ダンディリオンをコーラの方へ押しやろうとしてきたのだ。
とはいえ、ダンディリオンはそう簡単に屈する男ではない。参加者たちは忙しなく踊り、笑い、激しくぶつかり合っている。この混乱に乗じ、彼は花嫁の方へ流されずに持ちこたえたのだ。陽気な音楽が鳴り響き、周囲の世界がめまぐるしく回る。吟遊詩人はそんな狂気の中にもリズムを見出し、軽やかに窮地を脱していく。
切れのあるターンを数回繰り出し、まずは1人目の兄弟をやり過ごした。彼は笑みを浮かべ、躓き床に転げた2人目の体を踏みつける。3人目の手を取り華麗なピルエットを決めると、ここしかないというのタイミングで手を離し相手のバランスを崩した。しかし4人目には苦戦を強いられた。ダンディリオンが右へ左へと跳びはね、素早く方向を変えようとも、相手は鏡像のようにピタリとその動きに反応してみせたのだ。そこで詩人は、あえて一歩下がるという簡単な罠を仕掛けてみた。するとその間抜けは、やはりダンディリオンを真似て一歩退いた。彼はそのまま後退を続け、やがて踵を返す。そしてその場を後にした。近くの露店裏に逃げ込むと、コーラの悲痛な叫びが聞こえてきたが、それでもダンディリオンは振り返らなかった。
これで自由の身だ。が、まずは大切なリュートを探さねばならない。見捨てられた気分の彼は怒りを募らせ、ウィッチャーを探してガレットの路地をさまよい始めた。そして、ゲラルトがまだこの街にいることを祈り、すがる思いで厩舎へと戻る。しかしそこに馬の姿はなかった。彼は落胆して跪き、首を垂れた。ウィッチャーも、彼の馬も、大切なリュートも、もはやこの地を後にしている。ダンディリオンはまたしても独りになり、持ち物さえ奪われ、理不尽な運命に罰せられたのだ。
しかし悲嘆に暮れる彼の背後から、人影が現れる。その影はなんと、片手にリュートを持ち、もう片方の手に手綱を握っていた。ウォッカで枯れた声をした人影は「さっさと立て」と告げた。
ダンディリオンは振り返り、己の幸運に歓喜した。
これはまだ、2人の旅のほんの始まりに過ぎない――彼は確かにそう感じていた。
ゲラルト
ゲラルトは踊らなかった。
少なくとも、出来る限りそうなることを避けた。群衆の間を進むには、頃合いを見て跳び退くなり、強引に押し分けるなりすれば十分だったからだ。ウィッチャーはまたしてもダンディリオンを探し求める。彼は馬鹿げた伝統儀式が始まるや否や、群衆に呑み込まれてしまった。しかしゲラルトは、吟遊詩人の代わりに裕福な商人を見つけることとなった。年老いて見えるその商人は、遠くにいる婚約者の振舞いについて途方に暮れた様子である。彼女は果たして、哀れな愚か者にその心変わりを伝えたのだろうか。
ゲラルトは先へ進んだ。舞い踊る人々が行く手を阻もうとするが、彼を止めることはできない。盛大に演奏が鳴り響き、もはや会話もままならない状況だ。そんな狂乱のさなか、ウィッチャーはなんとか見つけ出す。鷺の羽根飾りがついた、あの特徴的な帽子を。そして帽子の持ち主は、やはりと言うべきか、見覚えのある4人の悪漢に囲まれていた。
さっさと片をつけたかったゲラルトは、全体重をかけて兄弟の1人を押しのけ、ダンディリオンから遠ざける。そして2人目を殴り、詩人の足元にひれ伏させる。ダンディリオンは馬鹿げた動きでクルクルと回るばかりだったが、その間にゲラルトは3人目の手首を掴んでいた。そのまま足を蹴りつけ、男の体を吹き飛ばす。だが4人目には手こずった。その主な原因はダンディリオンだ。彼は道化師のように振る舞い、男を出し抜こうと散々苦労した挙句にようやくその場を逃れる。男はダンディリオンを追う姿勢を一瞬見せたものの、すぐさま向きを変え、コーラの叫び声がする方へ向かった。哀れな少女は本来の求婚者の腕に固く抱きかかえられている。彼女の目は救い手となる詩人の姿を探し求めていたが、愛らしいその顔は惨めにも曇っていく。彼はもはやどこにも見当たらなかった。その頃ウィッチャーはといえば、余計な苦労にうんざりしつつ、厩舎へと戻って来ていた。
中に入り、吟遊詩人の姿を目のしたゲラルトはひとり微笑んだ。ダンディリオンは地面にひざまずいていた。少し左を見れば、ローチの鞍袋からはみ出たリュートが視界に入ることだろう。だがダンディリオンは、そのことにまるで気づいていなかったのだ。ゲラルトは笑ってリュートを取り出し、落ち着くよう彼に声をかけて惨めな茶番に終止符を打ってやった。
それからしばらく経ち、ガレットを出るべく門へと向かう道中、ゲラルトは馬上で振り返り、後に続く吟遊詩人のことを見た。ダンディリオンはどうやら、ウィッチャーと旅を続ける気らしい。
たとえ世界の果てまででも。