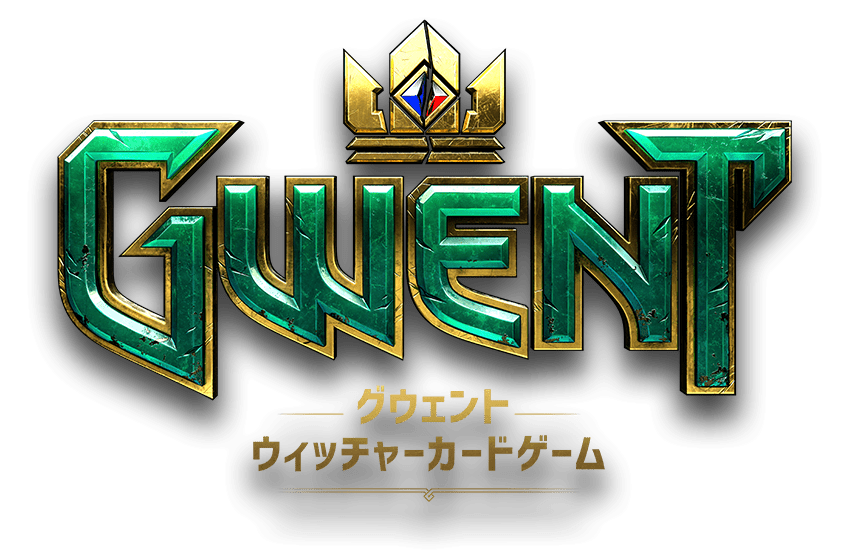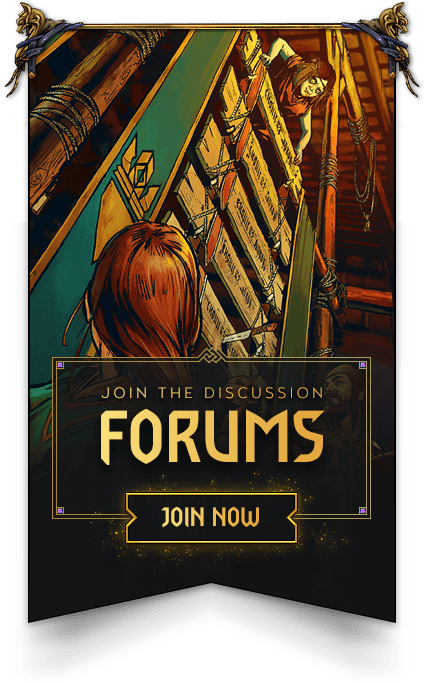「みんな死んでいた。もちろん私は別よ」ガランシアは陰鬱な調子で告げた。「でも他はみんな… ついさっきまで生きていた、愛する人たちがみんな…」
彼女が即席の聴衆を見やると、大きな碧眼のなかで焚き火の炎が舞った。彼らは皆、ぽかんとした表情を浮かべている。ドワーフの一団も、ハーフリングの仕立屋も、商人も、オクセンフルトの同僚たちも、誰ひとりとして彼女の話に口を挟もうとはしなかった。そして彼女は続けた…
「私たちは地方を旅してたの。毎年やってる巡業でね、娯楽に大枚をはたけるお客を求めて邸宅や酒場、売春宿なんかを訪ね回ってたのよ。あれは冷え込みの厳しいとある早朝のことだった。霧が立ち込める森は、神秘的な雰囲気に包まれていた。とても美しかったわね。一番前の荷馬車では、役者のジョエルとエルバが騒がしくしていた。前の晩から酔っぱらってて、大声でふざけ合ってたの。その場面はよく覚えてる。だってその次の瞬間…」彼女はそこで間を置き、緊張感を駆り立てた。「…悪夢が飛びかかってきたの」
ハーフリングの仕立屋は話に引き込まれ、目を丸くしている。ドワーフの何人かは首を振り、小声で下品な言葉を吐いていた。だがそれ以外の面々は様子が違う。蜂蜜酒に口をつけ、ボソボソと話しだしていた。怪物に襲われることなど日常茶飯事であり、もはや聞き飽きた話に興味を失っていたのだ。
「そこで突然、空気が変わった。鳥のさえずりがピタリと止み、優しく吹いていた風が止まったの。木々の間をもやが漂い、周囲を包み込んでいくように感じた。私たちを呑み込んでくかのように。そして気づくと、辺りは真っ白な霧に覆われていた。もはや何も、誰ひとりとして姿は見えなかった。
初めはそんな状況を楽しんでる奴もいたのよ。笑い声が聞こえてたんだけど、それも長くは続かなかった。恐ろしい鳴き声が彼らを凍りつかせ、その直後にゾッとするような金切り声が響いた。そしてそれがもう一度。頭上の霧の向こうに、次々と影が現れていた。私は急いで荷馬車から跳び下りて、その下に身を隠した。泥のなかで縮こまりながら、みんなが死んでいく音を聞いたの。おぞましい叫び声をあげながら、一人また一人と殺されていくなか、私にはどうすることもできなかった――だって、ほんの子供だったのよ」
「どうやって助かったんだ?」先が気になり、こらえ切れなくなった兵士がたずねた。
「うるさい。黙って最後まで聞け」とドワーフが怒鳴る。
彼女は頷いて感謝を示し、小枝を何本か火にくべた。「やがて仲間たちの声は聞こえなくなった。聞こえてくるのは、ずっと上の方で鳴いてる怪物の声だけ。私は恐怖で動けなくなって、身を隠したまま、ただ震えていた。ところがその時… ドスン、と何かが荷馬車に降り立った。そして目の前に、うろこに覆われた長い尾が垂れ下がってきた。すぐ頭上から荒い息遣いが聞こえる。神の類は信じてないけど、あの時ばかりは祈りを捧げた。すると、それに応えるかのように雷が霧を貫き、虹のような光が荷馬車の方へとやってきた。それから聞こえたのは、甲高い鳴き声。切断された尻尾が地面に落ち、周囲から聞こえていた鳴き声はたちまち悲鳴に変わり、霧の向こうで羽ばたいていた影が次々と弾けて血の塊と化していった。立ち込めていく焼けた肉の臭い。翼の生えた怪物の一匹が落ちてきて、血まみれの地面に横たわっていた。それは焼け焦げた体で弱々しくのたうち、悲痛な声をあげた。そして飛び立とうとして、力尽き、死んでいった。霧の向こうから彼が――私の救い手が現れたの」
「ふん!」と誰かが声をあげ、さげすむようにツバを吐いた。焚き火の光のすぐ外側で、木にもたれかかっていたマント姿の人物だ。ガランシアは頭巾を被ったその男に一瞬目をやり、無礼な態度に考えを巡らせたが、無視して話を締めくくることにした。
「怪物を全て退治すると、救い手は私の方にやって来た。平然とした様子でね。その指先では、純粋な力がパチパチと音を立てていた。彼は剣についた怪物の血を拭い、それを鞘に納めた。そして私の前にひざまずくと、朗々と響く滑らかな声で私をなだめたの。恐れることはない。もう安全だ、と」
忌まわしいあの日、深い霧のなかで、愛する人たちの死体に囲まれ、全ての希望が失われたかと思ったその時… 私の祈りは届いたの。でもそれに応えたのは神じゃない」そこでガランシアの目が輝いた。「私を救ったのは、かの名高き魔術師… アルズールだったの」
「吟遊詩人をやめたのは、それが理由なのか? スノードロップでいることをやめたんだろ?」ハーフリングの仕立屋がたずねた。
「そんなまさか!」とガランシアは返す。「むしろその時に始めたのよ」
「じゃあなぜやめたんだ? その歳なら今ごろ何百… いや何千って詩を書けてるはずじゃないか!」
ガランシアは頭を傾げて考え込んだ。フィドルを置いてからというもの、幾度となくされてきた質問だった。「人生には変化はつきものよ。そして多くの場合は、変化には従ったほうがいい」
回答をはぐらかされたハーフリングは不満げに唇を歪めたが、仕方なく頷いている。
「高名な魔術師様の話をもっと聞かせてくれよ…」兵士が前のめりに言った。
「ふん、なにが“高名”だ!」後ろにいた一人が吐き捨てた。ついさっきまで、ガランシアの話になど興味なさそうにしていた男だ。「“悪名高い”の間違いだろ! 奴は気のふれた反乱者だ。賞金首の分際が、少女を救う英雄だって?」
「おい、口に気をつけろ!」ドワーフが割って入り、またしてもガランシアの味方をする。「どう言おうと彼女を救ったのは事実だ。完全な悪人ってわけじゃないんだろう」
「でもどうして?」商人が腕を振りつつたずねる。「わざわざ子供一人を助けるなんて… ああ、悪く思わないでくれよ。でも魔術師ともなれば、他にやるべきことがあるもんじゃないのか? たまたま惨状に出くわしたもんだから、“ちょいと手を貸してやろう”とでも思ったのか? そんな偶然があるとは思えんな」
「お前の感想なんか知るか。それにもう少し頭を使ったらどうだ?」とドワーフが噛みついた。「魔術師は何でも見通せるんだ! おまけに転移だってできる! どこにだって一瞬で移動できるんだ。それぐらい、どんな間抜けだって知ってる」
「ああ、そうだな。いかにも間抜けの考えそうなことだ。でも問題はそこじゃない。重要なのは“どうやって”じゃなく“なぜ”の部分だ。だからもう一度言わせてもらう… どうしてだ?」
「それが英雄ってもんだからさ。そうだろ?」今度は別の聴衆が声をあげた。
ガランシアは微笑み、ワインに口をつける。彼女は白熱した議論が好きだった。そしてこれがいかに繊細な話題かをよく理解していた。
「彼らだって人助けをするさ!」
「どうだかな! 魔術師は冷酷で計算高い連中さ。そこらで人助けをして何になる? 何の得にもならないだろ?」
「怪物狩りをしてたんじゃないか? 薬の材料集めをしてたとか」
「そういうのは弟子にやらせるだろ」
「じゃあ気晴らしだったのかもしれない。ちょっとした息抜きに――」
「うぬぼれさ!」荒々しく、軽蔑に満ちた声が響き渡った。焚き火の周りが一瞬で静まり返る。「虚栄心を満たすためだ!」旅人たちは一斉に振り返り、マントの男に視線を向けた。男は焚き火から距離を置き、枯れたオークの根元に寄りかかっている。ヴィジマを過ぎたところで隊商に加わって以来、男が口を開いたのは初めてのことだった。彼らの多くは男が口を利けないか、頭が鈍いのかとさえ思っていたのだ。継がれる言葉を待ち、彼らは頭巾の男を見つめ続けた。だが男は黙り込み、影の中に佇ずむばかりだった。
「そうだな… ええと」奇妙な沈黙を破ったのはハーフリングだった。「思うにアルズールは、自分の力を示したかったんじゃないか? 騎士のように、高潔であろうとしたんだ」
「今度はなに?」ガランシアは興味深そうに応じた。「どうしてそんな風に思ったの?」
「実はだね、うちの先祖の一人が、アルズールの育った屋敷で働いていたんだ」彼はぼろぼろのハンカチで汗の滴る眉を拭った。「何かと昔話を聞かされることってあるだろ? それで子供の聞いたんだ。色々と――」
「はいはい! 前置きはもういいから」とガランシアが口を挟む。「さっさと本題に入って」
「ああ、そうだな。すまない。ああ… ええと、その… 全ての始まりはある子供との出会いだ…」
「いや、待ってくれ。言い方が悪かったな、すまない。子供というのは… アルズールのことでね。彼は私生児だったんだ。ある時、マリボー郊外の立派なお屋敷の前に、赤ん坊のアルズールが置き去りにされていた。『母親は死んだ。この子もあなたの子だ』と書き添えられてね」
仕立屋は倒木から跳び下り、焚き火の周りをうろつき始めた。劇の語り手を真似たのだが、上手くはいっていない。
「母親は近くの売春宿で働いている娼婦じゃないかと推測された。ところが屋敷にいた“高貴な男たち”は皆、道楽好きで有名でね。父親が誰なのか、断定できなかったんだ。とはいえ我が子かもしれない赤ん坊を狼の餌食にしたいとも思えず、子供は引き取られることになった。だが、それでめでたしとはならない。屋敷の男たちは必要以上に愛情を示せば罪を認めたも同然だと考え、子供と距離を置いたんだ。一方の女たちはと言えば、そんな彼を哀れみ丁寧に世話をした。だけど哀れみなんてものは、愛情の代わりにはなり得ない。
当然、兄弟姉妹からは卑しい生まれを馬鹿にされ、仲間外れにされた。その結果彼は、屋敷の図書室に引きこもるようになる。昼夜を問わず本を読み、驚きに満ちた世界や、勇敢な英雄たちの物語に夢中になった。なかでも特に心を惹かれた一冊があって、その本を毎週のように読み返していた。『騎士道精神への手引き』。著者は… メティナのマテオ卿だったかな。彼はすっかり魅了されたんだ。気高き騎士の行いと、皆に勇気を与える騎士道の美徳に…
そうして彼は、屋敷やその周辺をあちこちと歩き回り、試練を探し求めるようになった。己の美徳を証明したかったんだ。古き騎士たちのような気高さや慈悲の心、寛容さを示そうとして、しきりに人助けをした。周囲に認められようと、必死だった。
だがほんの子供に過ぎない彼には、勇気という美徳を示すことができなかった。物語の騎士のように、勇ましく戦う機会なんてありはしないからだ。わかるだろ?
だがある日、雑用で市場へ向かう道すがら、アルズールは盗賊に襲われている荷馬車を見つけた。普通なら一目散に逃げ出し、せいぜい助けを呼ぶぐらいしかできないだろう。でも彼は違った。彼には勇気を示す必要があったんだ。そうして、愚かにも盗賊たちと対峙した…
数時間後、気を失っているアルズールが発見された。彼は痛めつけられ、血まみれで道の脇に横たわっていた。かなりの重傷だ。回復には何週間もの時間を要したが、それでも彼は無事に回復した。そして驚いたことに、彼は自らの力を示そうと、より一層決意を固めていたんだ! しかも今度は、ただ機会を待っているだけじゃない… 自ら探し求めるようになっていた。
そしてまた、打ちのめされた姿で発見される。どぶに捨てられ、危うく死にかけていた! それでも彼は諦めなかった。似たようなことがその後も続き、彼は何度も大けがをして、何度も立ち直った。そんなことを繰り返していたある日、予想外のことが起きる。
アルズールがまたも行方をくらまし、貴族の男たちは妻に命じられて渋々捜索を行った。やがて彼らはアルズールを発見する。だけどそこにいたのは、今回ばかりは、血まみれで倒れている少年ではなかった。無傷の彼が、裏通りにじっと佇んでいたんだ。ショックを受けた様子で、目の前に積み重なっている3人の大男の死体を見つめていた。死体は黒焦げになっていた。
少年の体には混沌とした力が流れていたんだ。眠っていた大いなる力に火がつき、解き放たれたのさ。彼には魔術の才があった… だがそれを制御することはまだできなかった。家族は身の危険を感じ、力のある魔術師に少年を導くよう頼んだ。その才能を上手く活かせるようにと。そして彼は熟達した。導きを受けた結果、優れた名のある魔術師になったんだ。今夜、我々が話題の中心にしている、その魔術師に。
だけど思うんだ。子供時代の影響がまだ残っていて、幼い頃に魅せられた騎士道精神が、今も彼の奥深くにあるんじゃないかってね。だから彼は少女を救った。だから彼は、いつだってそうするんだ。
少なくとも、個人的にはそう思ってる…」
聴衆の幾人かがぼそぼそと語りだし、様々な意見が飛び交い始めた。だがそれも、ガランシアが口を開くと瞬く間に収まった。「面白い考えね」彼女は間を置き、ゴブレットを指で叩きながら考える。「確かに、子供時代の出来事はそれぞれの生き方に大きな影響を与える。だけどアルズールを突き動かしたのは、騎士道精神だけじゃないと思う。もっと強い何かが、その裏にあったはずよ。この世で一番強いものと言ってもいい…」
「そいつはいったい何だ?」ドワーフがたずねた。
「愛よ」
「愛だと?」商人が甲高い声をあげた。「なにが愛だ!! 大した理由もなくエランダー軍の半分を惨殺した男なんだぞ!?」
「聞いて。愛と言ったのにはちゃんと理由があるの」とガランシアはなだめる。「私とアルズールが二度目の邂逅を果たした時に、分かったことがあるの。その時も私は彼に救われた。二回続けてね」彼女は笑った。「不幸な運命に翻弄された私は… 呪いにかかっていたの。奇妙な呪いだったわ! その力は私の歌い手としての技量に大きな影響を与えてしまったの」
ハーフリングがハッと息を呑んだ。「そうか! それで吟遊詩人をやめたのか!」
「いいえ、むしろその逆よ。呪いの力によって、私の凡庸な旋律は魅惑的な歌に変化を遂げた。だけどその代わりに私は――歌うことしかできなくなってしまった」彼女の顔に笑みが浮かぶ。「何か話そうと口を開くたび、とめどないリズムと押韻がひとりでにあふれ出たの」
聴衆の一部から笑いが起きた。ガランシアが愉快な話をしていると思ったのだ。
「最初はとても奇妙で、風変わりなおかしさがあった。歌に支払われる報酬も馬鹿にできるものじゃなかった。でもね、お金は別として、その力はすぐ負担になった。明けても暮れても、延々と歌い続けるなんて。何でもないひと言を口にしたくても、大層な詩の連なりがあふれ出てしまうんだから。やがて私は助けを求めることにした。決定打になったのは、ある恥ずかしい経験をしたから。とある葬儀に参列した時のことよ。そこで私は愚かな選択をした。人に場所をたずねたのよ。つまりその、どこで…」ガランシアは頬を赤らめた。「用を足せるかって。あの時の恥ずかしさが蘇りそうで、あそこには未だに戻れない」そう言って彼女は肩をすくめた。「解決策はなかなか見つからなかった。だけど何ヶ月も経ったある日… 狡猾な運命のめぐり合わせが再び起きて、私は田舎町のとある宿屋にたどり着いていた。とある魔術師と同じ宿屋にね…」
「私はアルズールに助けを求めた。今回も力になってくれると思ってね。ところが彼は、他にもっと重要なことがあるからと協力を拒んだの。妄想になど付き合ってられないから他を当たれって。だけど私は諦めなかった。彼はまだ、私がどれだけの頑固なのかを知らなかった。だから思い知らせてやったの… 3日間ずっと、私の歌を聞かせ続けてね。バラッドに子守唄に詩から聖歌まで、思いつく限りの歌という歌を歌い続けた。当然彼は魔術で私を黙らせようとした。でもできなかった――それだけ強力な呪いだったの。彼はついに根負けして、頼むからもうやめてくれと懇願した。力を貸すから口を閉じてくれ、とね」
「それで? 愛の話にどう繋がるんだ」兵士がたずねた。
「そうね。私たちは呪いの発端となった町を目指したの。途中途中で宿に泊まりながらね。そしてある晩、アルズールが地元の人たちと夜遅くまでお酒を飲んだり、賭け事をしたりしていて… あの頃の私はひどく詮索好きだったから… それで、彼の持ち物をこっそり物色しようと思ったの。奇妙で素敵な装飾品がたくさん出てきた。なかでも子供だった私の興味を引いたのは、花を象ったメダル。ユリの花よ。それを試しに着けてたら… アルズールが部屋に戻って来て…」
「彼はもの凄い剣幕で怒鳴り、私を叱った。すごく怖かったんだけど… 同時に困惑もした。高価なメダルには見えなかったし、壊したわけでもなかったから」そう言って彼女はニヤリと笑った。「あの時の私には、感傷ってものが分かってなかった。でも彼はすぐに平静を取り戻し、怒鳴ったことを謝りさえした。そして暖炉の前に座ると、酒の匂いを漂わせながら、じっと炎を見つめた。怒りは悲しみに取って代わられていた。それからなんと、自分の過去を打ち明けてくれたの」
「そのメダルは彼がずっと以前に作ったものだった。彼の… 大切な人のために。その人を守るために、魔法までかけてあったのよ。『リリアナ…』彼はそう囁いた。そして彼女との思い出を、酔いの回った口でぼそぼそと、愛おしそうに語りはじめた。彼女の野心を称賛してね。話を繋ぎ合わせて分かったのは、彼女がより安全な世界を夢見ていたってこと。恐ろしい怪物が影に潜むことのない、穏やかな世界よ。本当に壮大な夢よね。その実現に全てを捧げた彼女の生涯は、残念ながら短いものに終わってしまった。少なくとも、魔術師の基準で考えればね」
「彼女の最期については何も語らなかった。酔ったまま黙り込んで、目には悲しみを浮かべていた」ガランシアはそこで間を置き、追想にふける。「『愛』って言葉は一度も使わなかったけど、彼の話し方や、彼女のことを懐かしむあの表情に… それ以外解釈の余地はなかったと思う」
「なるほどな」とハーフリングが頷いた。「待てよ… もしかして、彼女が死んだ後、彼はその夢を引き継いだのか? そうなんだろ!?」
「ええ、そうだと思う。亡き者との約束は、そう簡単には断ち切れないものだから」
「ふん!」ドワーフが勢いよく立ち上がり、商人の方を向いた。「聞いたか? 奴が怪物から人を守るのには、そういうわけがあったのさ! これでご納得いただけたか?」
侮辱的な物言いをされても商人は意に介さない。「そうは言っても、どうやって引き継ぐんだ? 大陸を駆け回り、死んだ恋人の妄想を掲げ、ひとり怪物退治に精を出して何になる? それで怪物がいなくなるのか? 何も変わらないさ!」
「ひとり? それは思い違いよ」ガランシアはいたずらっぽく笑ってみせた。「ひとりだなんて、とんでもない…」
「…ウィッチャーか!」兵士が声を荒げた。「そいつはウィッチャーのことだな!」
「今度はなんだ?」洋皮の水筒から酒を注ぎつつ、商人がたずねる。
「ウィッチャーさ。そう呼ばれてるのを聞いたことがあるぞ」兵士はそう言って、ひげの濃いあごを掻いた。「あれはそうだな… 傭兵みたいなもんさ。ただし、魔術で強化された傭兵だ。人間の比じゃないぐらい強くて、動きも素早い。ひとりであちこち旅しながら、怪物退治を請け負って金をもらうのさ」
「デタラメだな」
「なんだと? 何も知らないくせに」
「傭兵と言ったよな? だったら、その手のことに詳しい奴に聞いてみよう」彼は手を上げ、影に佇むマントの男のほうを指し示した。「ちょうどいいことに、あいつ自身が傭兵だからな。いや、傭兵というより、裏世界の殺し屋って感じか。そうだろう、殺し屋さん?」
マントの男は返事代わりに唾を吐き捨てた。それを見た商人が下品な笑い声をあげる。
「ちょっとばかり態度は悪いが、腕には定評がある――本当さ。俺もこの目で見た。マリボーまでの道のりに、用心棒を探してたからな。安全に送り届けてくれたら金を払うと持ちかけたのさ。いい話だったよな?」そこで長い間ができた。「話がそれたな。それでだ、殺し屋さん! 剣を振るって金を稼ぐ同業者として、“驚異の怪物狩り”の話をどう思う?」
マントの男は首を傾げ、少しのあいだ考えた。「人が怪物を殺したって…? 何も驚異に値しない。下らんおとぎ話だな」
「そら、聞いたか!」商人は高らかに告げ、調子のいいニヤケ笑いを浮かべた。「下らんおとぎ話だ!」
「いいや、そんなことはない! 信用できる連中から聞いた話だ。あちこちで全く同じ話を聞いたんだぞ? そいつらが全員、たまたま同じ嘘を思いついたって言うのか?」
「妄言はすぐに広まる。往々にして、真実よりも速くな」
兵士は首を振った。「いやいや――」
「まあ聞け。あんたのお友達が全くの嘘をついてるとは言わない。勇敢な奴らが束になって、怪物を打ち倒すことだって時にはあるだろう。その腕前を否定する気はない。だがな、“魔術で強化された傭兵”なんてのは、どう考えたって戯言さ。それにもし――」商人は切り株から跳び起きて地面の石を掴み取ると、近くを動き回っていた2匹の鼠にそれを投げつけた。
鼠たちは甲高い声をあげ、やぶの中へと逃げ込んだ。
「なんの話だった? ああそうだ。それにもし、その“ウィッチメン”とかいう――」
「ウィッチャーだ。ちゃんと聞こえてたろ!」
商人は腕を振って応じる。「そうだ! そうだったな、“ウィッチャー”だ! そのウィッチャーとやらが、あんたやお友達の言うように実在するとして、そんなものが本当に必要か? 怪物ってのは、そこまで恐ろしい脅威か? そりゃあ確かに、不運な間抜けが殺されることはある。だがそんなの自業自得だ。考えなしに道を外れるような間抜けだから、暗い沼地の奥やらで怪物の餌食になるのさ」
「お前は何も分かってない。そんな無茶苦茶があるか!」ドワーフが怒鳴った。
「大いに必要だろう! 安全な旅路の確保に金はかけたくないか? なら危険のない場所でじっとしてることだな。俺のように立派な護衛役を雇える財力はないか? だったら地方を歩き回るのはよして、都市部に引きこもるんだな。それにだ。よくよく考えてみれば、怪物だって俺たちのためになってるのかもしれない… 社会のクズを始末して、間引きをしてくれるんだからな」
兵士が歯ぎしりをして怒りを露わにする。「偉そうに言ってくれるじゃないか」
「これまで何を聞いてたんだ? 耳が遠いのか?」彼は殺し屋のほうへ頷いてみせた。殺し屋は野営の端の辺りをうろついている。「さっきも言ったが、身の安全には気を遣うほうでね。だからどんな事態にも十分な備えをしている」
「ならひっぱたかれないよう備えときな。いつまでもウダウダ言いやがって」とドワーフが食ってかかる。
「――黙れ!」と殺し屋が言った。彼は足を止め、焚き火の向こうの暗闇に頭を向けて、何かをじっと見つめている。「静かにしろ。バカ騒ぎをするにはもう遅い」剣の柄頭に手を置き、野営から離れていく。
「待ってくれ」そこに商人が声をかけた。「どこへ行く気だ? おい、殺し屋!?」しかし殺し屋は何も応えず、夜闇の向こうへ消えてしまった。
「彼の言うとおりね」ガランシアが言った。「もう遅いでしょ。老いた骨をそろそろ休ませないと」彼女は立ち上がり、テントに向かう。「明日は忙しくなるわよ」
「はいよ」とつぶやき、ドワーフは蜂蜜酒を飲み干した。「そいつは確かだな」
1時間後には全員が床に就いて熟睡していた――起きているはずの、見張り役までもが。
…そのとき、近くの影に浮かび上がるものがあった。淡い月明りの下で、一対の赤い眼が丸く輝いていた。
いびきの音が野営に響き渡り、消えかかった焚き火がパチパチと音を立てていた。その遥か上では、雲の隙間から満月の光が差し込み、炎の光が届かない場所を不気味な白黒調に染めている。
テントのひとつが波打ち、寝ぼけた様子の商人が外に転がり出た。彼は近くにある大きな木の影を見つめ、そちらに向かって歩きだす。炎のそばには寄り集まって眠る旅人たちがおり、彼はその間を縫うように進んだ。
やがて人目につかない暗がりを見つけた彼は、ズボンの前を開けて用を足し始めた。だがそのとき――
キーッ!
甲高い声がして、商人は思わずよろけた。音のほうへ振り返りながら、自分の足を濡らしてしまう。「ちくしょう!」
近くの切り株に鼠がいて、商人のことを見つめていた。キーキーと、笑い声のような音を立てる。
「この野郎!」彼は叫び、片手いっぱいに掴み取った小石を投げつけた。「失せろ!」
しかし鼠は微動だにせず、甲高い声で挑戦的に鳴くだけだった。
「ふん!」と言って、商人は周囲を見回した。「なら思い知らせてやる――よし、こいつがいい!」大きな石を持ち上げ、鼠のほうへ運ぶ。「警告はしたからな――おら!」彼は石を投げつけた。鼠はその場から跳び退き、近くの茂みに逃げ込んだ。
「ハッ!」彼は満足げな笑みを浮かべる。「もう二度と――」
キー、キーッ!
商人は跳び上がって振り返った。狡猾な鼠が一匹、彼の背後に回り込んでいた。
「お前、いつの間に――」
キーッ! キーッ! キーッ!
茂みの中から次々と鼠が現れ、彼を取り囲んでいく。
「ど、どうなってんだ…」と彼は呟いた。
月明りの下で、商人を見つめる大量の鼠たちの目がきらめいている。
「殺し屋?」彼は囁く。「おい、殺し屋… ど、どこに行っちまったんだ…?」
そのとき、一帯を影が覆った。影は商人の頭上に現れ、月の光を遮っている。彼は震えながら振り返った。「殺し屋か?」だがそこにあったのは、こちらを見下ろす一対の緋色の眼だった。口から泡を溢れさせ、長い切歯から唾液を滴らせている。
商人は恐怖のうめき声をあげ、次の瞬間、喉を切り裂かれていた。
鼠の大群が野営を駆けめぐり、旅人たちはテントやそれぞれの眠っていた場所から次々と転げ出た。大混乱のなか、様々な声が飛び交う。
商人の胴体が投げ飛ばされて野営の真ん中に落ち、それを見た誰かが叫んだ。そして影の向こうから、獰猛な巨獣が姿を現した。剥き出しの筋肉と傷のついた体が、恐ろしい印象を放っている。獣はうなり声をあげて巨大な口を震わせ、突進してくるドワーフに強打を食らわせた。ドワーフは軽々と吹き飛び、闇の彼方へと消えていく。
巨獣は忙しなく眼を動かし、やがてガランシアに視線を定めた。彼女は戸惑いながらテントを出たところだった。獣は歯ぎしりをして彼女のほうへ向かっていく。うなり声をあげ、よだれを垂らしながら。
バシッ!
石弓から放たれた矢が肩に刺さる。獣は叫び、矢を抜き取った。荒々しく口を開き、攻撃者を探す。
ドスッ!
別の矢が命中する。今度は胸に刺さっていた。
「下がっていろ!」殺し屋が茂みから駆け出し、石弓を捨てて剣を抜く。振りかざされた刃が、銀色のきらめきを放った。
獣は大きなうなり声をあげて彼に襲い掛かった。殺し屋は剣を持ち上げ、ギリギリまで耐えて好機を伺う。そして… 左へ身を翻し、大きく振りかぶった一撃で獣の背中を斬りつける。辺り一帯に血しぶきが降り注いだ。
その後には魅惑的なまでの乱撃、牽制、突き返しが続いた。血が吹き出し、獣の叫びが響き渡るなか、マントの男は堂々と主導権を握り、圧倒的な速さと卓越した正確さで次々と獣を斬りつけていった。
激しい傷を負った巨獣は哀れな声を漏らし、よろよろと膝をついて前に倒れ込んだ。巨体の周囲に血だまりが広がっていく。
殺し屋は剣を構え、とどめの一撃を繰り出さんとしている。
だがそのとき、見守っていた一人が息を呑んだ。獣が素早く腕を伸ばし、殺し屋の喉元を掴んだのだ。獣はうなり、立ち上がって彼の体を高く掲げた。醜い体の傷は既にふさがっていた――切り裂かれた肉や筋肉が再生していたのだ。殺し屋は剣を捨て、喉元に絡みついた手を引き剥がそうとする。
周囲で見守っていた者たちは凍りつき、獣の手中でもがく殺し屋を呆然と見つめていた。しかし次の瞬間、彼らは驚愕する。殺し屋が獣の顔に向かって手を伸ばし、指で奇妙な形を作ったのだ。
するとその手から炎が放たれ、獣の顔から胸にかけてが焼き払われた。獣は悲鳴をあげて彼を手離し、自分の鼻先を掻きむしりながら後ろによろめいた。
殺し屋は導火線のついた革の球体を素早く取り出し、指先でパッと火をつけると、喚く巨獣の足元にそれを投げた。
爆弾はシューッと音を立ててから火花をあげ…
ドカン!
轟音を伴いワーラットを吹き飛ばした。その体は、黒焦げの肉片と骨に成り果てる。
旅人たちは飛び散った血と内蔵にまみれ、圧倒されてその場に固まっていた。
殺し屋は商人の無惨な死体に歩み寄って鞄を探り、ジャラジャラと音を立てる袋を取り出した。彼はぽかんとしている見物人たちの顔を見やり、肩をすくめると自分の懐に金を収める。
大きく口を開けたままの兵士が、震える指でマントの男を指して言った。驚愕しながらたった一言、「…ウィッチャーだ」と。
照りつける日差しのなか、隊商はマリボーを目指してほこりっぽい道を進んでいた。集団後方ではガランシアが荷馬車の後ろに座り、ウィッチャーが馬でゆっくり近づいて来るのを見つめていた。
彼女は親し気な笑みを浮かべて言う。「昨夜はありがとう。心から感謝してる」
称賛の言葉を嫌がり、彼は眉間にしわを寄せた。それでも受け入れ、仕方なさそうに頷いてみせる。
おかしな考えが頭をよぎり、ガランシアはクスクスと笑った。「見方によっては、またしてもアルズールに救われたってわけね」
ウィッチャーは歯を食いしばり、鼻の穴をふくらませる。
「どうかしたの?」彼女は尋ねた。「感謝の言葉が聞きたくてこっちに来たわけじゃないんでしょう?」
彼は少し間を置いて考えをまとめる。「アルズールを知っているんだよな?」
「ええ、彼のことならよく知ってる」
「ならどうして、あんなデタラメを言いふらす?」そう言って彼は首の骨を鳴らした。「単に妄想に囚われてるのか、真実がまるで見えてないのか」
彼女は微笑えんだ。「真実は必ずしも普遍的なものじゃない。時にそれは、視点の問題に過ぎない」
ウィッチャーは低くうなったきり黙り込み、しばらくしてから苛立たしそうに首を振った。「“愛”だと…?」彼はそう吐き捨てる。「他者を思いやる気持ちがあったら、あんなことは絶対にできないはずだ。今だって続けてるに違いない」
「何か言いたいことがあるようね」ガランシアはウィッチャーを見つめ、あくびを噛み殺した。「昨日は眠れなかったの… 分かるでしょ。だからさっさと話して。私の意識がはっきりしてるうちに」
「アルズールがどうやってウィッチャーを作るか、その方法を少しでも知っているか?」
「愛の力ではないんでしょうね…」
「連中は小さな子供を連れ去る。通りで捕まえてな。必要なら親に金を渡すこともある。あらゆる手を使って、実験台を確保するんだ。子供でないといけないらしい――俺はそう聞かされた。コジモという年寄りの魔術師がいてな。白髭を生やしたそいつはよく… “展性”がどうとかと捲し立ててたな。コジモとアルズールは、俺たちを鋳造に使う粘土板として扱っていたんだ。平然とな。奴らはこう言っていた。長く生きてると、その年月に応じて粘土は固まっていく。だから成長しきった人間を再形成するのは不可能だ。バラバラに割れてしまうから――とな。そういうわけで、変異実験には子供しか使えない。といっても、変異に耐えられる可能性があるというだけだ。子供だろうと、そのほとんどは割れる」ウィッチャーはガランシアを見つめ、その反応を伺っている。「俺の知る子供たちも、大勢が無惨に死んでいった」
彼女はウィッチャーの視線を避け、道の脇の牧草地を見やった。
「確かに… 死んだ子供たちは、あまり良いバラッドの題材にはならないわね」
そしてウィッチャーに視線を戻すと、そのまま黙り込んだ。彼女の目には好奇心が満ちている。
「死体を埋めるのは俺たちの役目だった。ズタズタの体に、歪んだ顔――断末魔の表情そのままに、口が大きく開かれていた。だがそういう子供は幸運だったのさ。早く終わりを迎えられたからな。生き残った哀れな者たちは、アルズールの様々な“試練”に耐え続けなければならなかった。なにが“試練”だ。それじゃあまるで、英雄的偉業を求めて自ら挑戦したみたいじゃないか。奴に認められるために、俺たちが進んで地獄に飛び込んだと言うのか?」
「奴がより良い世界を夢見ただとか、そんなことを言っていたな。だが俺に言わせれば、そんなのはデタラメだ。奴は自分のことしか考えない。虚栄に過ぎないのさ。人助けなんて… 結果的にそうなることもあるだけだ。思いやりの気持ちを装うことがあっても、それは人の目があるからだ。奴の計画に出資する間抜けどもが訊ねて来る時とかな。そうさ、貴族連中にはとことん良い顔をする。俺たちを連れ回す時なんて、ずいぶんなもてなしをするからな。自分の功績と天才ぶりをこれでもかと見せびらかすんだ。“さあさあ、偉大なるアルズールが生み出した奇跡をどうぞご覧あれ”なんてな。思い上がった野郎だ」そう言って彼は鼻を鳴らす。「満足した出資者たちが帰れば、奴は一瞬で冷酷さを取り戻し、自分の塔へ帰っていく。そして次の試練の準備が整うまで、姿を見せることはない。俺たちには楽しくない時が待ってるのさ。俺たちは目的達成の手段でしかない――奴が評判を得て偉業を残すための道具だったんだ」考え込む彼の目が、どんよりと曇る。「…奴の思うままに形を作り変えられる、手の中の粘土さ」
そこで長い間ができた。
「すごく引き込まれる話だった」と言って、ガランシアはニヤリと笑う。「語り部として食べていけるんじゃない?」
「嘲りたければ好きにしろ。だがこれが真実だ――視点など関係ない」彼は咳払いをして唾を吐くと、再び過去に思いを馳せはじめた。
思索にふけりながら荷馬車と並んで進むウィッチャーを、ガランシアは見つめ続けた。
「ねえ…」彼女は慎重に言葉を選び、話しはじめる。「昨日はあなたがいてくれて本当によかった。感謝してるの。あなたには、そのことを知っていてほしい」
ウィッチャーは少しためらってから頷いた。「俺は前に出ていよう… 道の先に危険があるとまずいからな」彼は瞬きをして思い出を振り払い、手綱を握りしめる。「ゆっくり休んでいろ」――そして駆け出した。
ガランシアは荷馬車の後部で体をもたせ掛け、雲ひとつない空を見ながら体を休めていた。重いまぶたでゆっくりと瞬きをして、前方から聞こえる規則的な馬の足音に耳を澄ます…
…遥か上では、鳥の群れが広大な青空を舞っている。そのうちの一羽が地獄のごとき金切り声をあげた。彼女は目を細め、それが鳥でないことに気づく。大きなギザギザの翼を時おりはためかせ、その背後ではうろこに覆われた長い尾がうねるように動いている。空を舞う怪物は急降下し、隊商に襲い掛かってきた。誰かが叫び声をあげ、次の瞬間には肉塊と化している。さらにもう一人、それからもう一人と犠牲者は増え続け、血と内臓の雨が降り注いだ。
アルズールの声がこだまする――「恐れることはない。もう心配はいらない」
深紅の豪雨が町役場の外壁に打ち付け、透明な水に変じていく。その窓からは暖かな光が放たれていた。
建物の中では、衰弱した人々が咳をしたり苦しそうに息を荒げたりしながら身を寄せ合っていた。男も女も子供も、体を震わせ、すすり泣いている。黒い外套とくちばし状に尖ったマスクをまとった人物が現れ、探るように杖で彼らをつつきながらその合間を進んでいった。
箱を並べて作った即席の舞台に、若き日のガランシアの姿があった。彼女は男っぽい吟遊詩人の衣装をまとい、青ざめた聴衆にフィドルを演奏して聞かせ、陽気な歌をうたった。彼らは落ちくぼんだ目に歪んだ喜びの光を灯し、苦しみの渦中から笑顔を浮かべている。
しかしそこで、冷たい響きのしわがれ声が告げた。「ああ、かわいそうに。病魔がお前の内にある。お前の深奥に巣食っている」
ガランシアは演奏を止めて楽器を下ろした。その目が大きく見開かれる。彼女の前に、死体の山があった。裸の体はしおれ、腐敗している。全員がくちばし状の尖ったマスクを着け、そのひとりずつが「カー」と鳴きはじめ、その声はどんどん大きくなっていく。かすれた鳴き声の交響曲が、周囲をすっかり呑み込んだ。
ろうそくの火が消え、完全な暗闇と奇妙な静寂が部屋に訪れた。
「死が立ち現れ、お前の光は消える」闇の中に2つの目が光る。「だが心配はない、我が子よ。老いしセルマが汝の腐敗を癒してくれよう」
中央の囲炉裏で炎が燃え上がり、小屋の内部が照らし出された。様々な装飾品や小物類が部屋の周囲に高く積み重なり、棚や垂木にはカラスたちが並び、跳びはねながら鳴き声をあげていた。
若きガランシアは細く青ざめた姿で炎の前に座り、反対側にいる黒い羽根をまとった老女を見つめていた。
「誓いを立て、汝の歌を聞かせよ」彼女は若き詩人に歯を見せた。「さすれば老いしセルマの力によって、汝は生き続けよう」そう言ってクスクスと笑う。
囲炉裏の炎が大きく燃え上がり、木の床にこぼれ出て壁を登り、全てを呑み込んでいった。
ひと気のない林の真ん中で、小屋が激しく燃えている。轟々と燃え盛る炎のなかを、痛ましい叫びが響き渡った。「ああ! 何てことを!?」
ガランシアは林の中に立ち、潤んだ目で激しい破壊の様を見つめていた。
アルズールの声が響き渡る。「ただ頷くのだ、スノードロップ。何も心配は要らない」
彼女は肩を掴まれ振り返った。すぐ隣にアルズールが立っていた。その顔と胸は血に覆われている。アルズールは彼女の前に跪き、あくどそうにニヤリとした。「これで二度目だな」と笑う。
林は炎に呑み込まれた。
そしておぞましい悲鳴がどんどん大きくなり――
ガランシアは目を開け、座ったまま背筋を伸ばした。その肌は汗に濡れている。
呼吸を整えながら周囲を確認すると、荷馬車は既に停まっていた。
近くで言い争う声が聞こえ、甲高い声が叫んだ。「こっちは本気だ! 聞こえたろ? と… とっとと下がれ!」
彼女は荷馬車の後部から跳び下り、一団が十字路沿いの宿屋の隣に停まっていることを確認した。木の看板には「複十字」とある。
荷馬車の後部から回り込むと、農民服をまとまった男女の集団が見えた。彼らは錆びついた剣や大鎌、熊手を手にし、隊商を取り囲んでいる。その真ん中で、ひょろ長い体型の女が石弓を構えていた。張り詰め、震える手つきで握られたそれは兵士に向けられている。
兵士は女に一歩迫り、「馬鹿な真似はよせ」と告げ、さらに一歩近づいた。少々威圧的に過ぎる態度だ。「なにもそんな――」
ビン、と弓の弦が弾かれた。
飛び出した矢が兵士の膝に刺さる。彼はうめき声をあげて矢を握りしめ、地面に倒れ込んだ。「このクソ女め!」
「け、警告はした。そうだろ?」彼女は口ごもり、周囲の見物人たちを素早く見やった。「全員、ふざけた真似はするな。分かったな? 従わないと… 同じ目に遭うぞ!」彼女は張り詰めた様子で叫び、慌ただしく次の矢を装填する。「文句のある奴はいるか?」
旅人たちは押し黙った。
「よし!」女は仲間のひとりに頷いた。「こいつらを中に入れろ。さっさと片づけるぞ」
「まったく、とんだ災難だ」とドワーフが苦々しい表情を浮かべる。彼は次のろうそくに火を灯し、地下室の隅の樽にそれを置いた。
「気をつけてくれよ」ハーフリングが警告する。「一難去ってまた一難。鍋の中から火の中へ… なんてご免だからな」
「心配すんな。俺の腕は石のごとき安定ぶりさ」ドワーフはまたろうそくに火をつけ、それを棚に置く。「それで? お前はいつからここにいるんだ」彼は大きな樽に腰かけている宿屋の主人にたずねた。
「ああ… そう長くはない。2、3日だろう」彼は旅人の一団を眺めやって続ける。「君たちが初めてだよ。連中が…」
「略奪に成功したのは?」ドワーフが割って入った。
「ああ、すまない。悪くとらないでくれよ。でもあいつらは、盗賊じゃないんだ。大半は私も知ってる連中さ。地元の農民やその手伝いが主だ。しかし… 忌まわしい干ばつが長引いて、みんな追い込まれてる――完全に希望を失ってるんだ。だからあんな真似を」
ガランシアが兵士の血まみれのひざに巻いた布を締めると、彼はうめき声をあげた。
一団の頭上で床板を踏みつける足音が聞こえ、天井から塵が落ちてくる。くぐもった話し声も聞こえていた。
「彼のことは気の毒に思う。連中だって本気じゃなかったはずだ」
「心配すんな。こいつなら大丈夫だ。だろ?」
兵士は低くうなった。
「しかしもう、兵士として戦うのは無理じゃないか?」とドワーフが笑う。「見張り役の仕事に慣れないとな!」彼はニヤリとして、石油ランプに火を灯した。そして奥の壁に立て掛けられた絵を照らす。巨大なキャンバスに広大な戦場が描かれていた。一方の陣営が白黒の旗を掲げて勝利を祝福し、もう片方の陣営は空から次々と炎が降り注ぐ下で縮こまっている。勝者の一団のなかに、高名そうな魔術師の姿があった。彼は堂々とした様子で腕を上げ、その周囲でルーンが輝いている。「終わりなき戦争の最終決戦さ」と宿屋の主人が説明した。「“アルズールの複十字”… それが題名だ。ここにはエランダーからの客が多いから――といっても、それも昔の話だが――その絵を飾っておくのはきまりが悪くてな。こっちにしまったんだ」そして彼はクスクスと笑った。「宿屋の名前までは変えれないがね」
「つまりあの話は本当だったのか?」ハーフリングがたずねた。「アルズールが魔術で軍に加勢したと?」
ドワーフはランプを持ち上げて絵がよく見えるようにした。「ふん。そうらしいな」
頭上で人の動きがあり、天井からまた塵が落ちてきた。不鮮明な声がさっきよりも音量を増している。
「アルズールのことを知っているのか?」宿屋の主人がたずねた。
「ちらほらと話に聞いてるな」ドワーフは絵を観察し、炎のなかで逃げ惑う兵士たちの姿を見ている。彼らは叫び、倒れていく。「こりゃあ勝ち目がない」
宿屋の主人は樽から立ち上がり、絵のほうへ歩み寄った。「この絵には描かれてないが、彼は〈門〉を開いたと言われている。呪文を使って恐ろしく強大な何かを呼び出したんだ… 別の世界から。伝え聞くところでは、空が裂け、渦巻く炎が戦場を包み込んだらしい。だがそれは、ドラゴンとかその手のものではなかった。もっと… おぞましい何かが…」彼はそこで口髭をなでた。「兵士たちを襲ったんだ。それが何であれ、彼らに打つ手はなかった。エランダーは降伏する他なく、翌日にはヴィジマの玉座をマリボーの公爵に明け渡していた。そうして終わりなき戦争は終結した」
「ひでえ話だ」ドワーフは蔑み、キャンバスをまじまじと眺めている。「イカサマだろ。戦いってのは、誇りをもって対等に行われるべきだ。別世界の化け物を使うなんて反則だ。こんな死に方をした兵士たちが哀れでならない」
「ああ。確かにそのとおりだな」とハーフリングが応じる。
「彼は…」ガランシアは物憂げな目つきで兵士から顔を上げた。「…命を救うためにやったのよ」
ドワーフが下品な笑い声をあげた。「おいおい、お嬢さん! そいつは矛盾した話だな!」
「いや、彼女の言うとおりだ」宿屋の主人が言った。「あの戦は本当に酷いものだった。この辺りでは無惨な流血が何世代にも渡り、際限なく続いていたんだ。どちらの公爵が少し大きな玉座に座れるかという、そんな些細な問題のためにな」
「争いについては聞いたことがあるが、それにしても… どうしてそこまで長引いたんだ?」ドワーフがたずねた。
「そうだな」と言って、宿屋の主人は樽に腰かけ直す。「両陣営の戦力が拮抗していたんだ。おかげでどちらかが圧倒的に勝利を重ねることもなく、膠着状態がいつまでも続いた。その結果、どちらにも勝利の希望が残り続けたんだろう。どちらも決して引き下がらず… その息子も引き下がらず… さらにそのまた息子も、という具合にな。戦場には次々と兵が送られ… 戦死者は増え続けた。責務を果たすため、栄誉のため、誇りのため――貴族連中は方便を並べ立て、人々の犠牲を正当化した。“犠牲”だなんて、そんな言葉で済むことじゃない。この辺りの家は、どこもあの忌々しい戦争で先祖を何人も亡くしている。そうでない家を探すのは相当骨が折れるだろう」
ドワーフは重々しく首を振った。
「アルズールが手を貸さなかったら…」宿屋の主人は話を締めくくる。「あの悲劇がいつまで続いていたか分からない」
ドワーフは眉間にしわを寄せた。「だが… 正しい行いとは言えないだろ? そんな風に… 他人の運命に干渉するなんて…」
「他人の運命に干渉する…」ガランシアは微笑んだ。「彼が何より得意とすることね」
上階からけたたましい叫びが響き渡った。
ドスン!と重い音がそれに続いた。
ウィッチャーはほこりっぽい道を引き返していた…
隊商にとって朗報なのは、待ち受けていたのが動物の死骸ばかりだったことだ。剥き出しになった骨が、畑のあちこちに転がっている。干ばつの犠牲になったのか。ウィッチャーはそう考え、死んだ動物たちを哀れに思った。
彼は十字路の宿屋のほうへ進んだ――隊商は既に着いている頃だろう。今夜はここに泊まるはずだ。それから半日も進めば、マリボーに到着する… 彼は眉間にしわを寄せ、はたと考え込んだ。俺はいったい何をしている? 報酬ならもう手に入れた。雇い主が死んだ今、特に何かを果たす責任はない。少なくとも、仕事のうえではそうだ…
彼は咳払いをして地面に唾を吐いた。まあ、これは暇つぶしだ。そう結論付ける。他にすることもないのだから…
宿屋のそばまで来ると、見覚えのある馬と荷馬車が視界に入った。予想どおりではあったが、奇妙な違和感が拭えない。何かがおかしい…
彼は慎重に駆け寄り、馬上から地面の跡を観察した。鞍から跳び下り、しゃがみ込んでよく調べてみる。争いの跡だ。乾いた血の染みも残されている――間違いない。彼は顔をしかめた。「まずいぞ」
ウィッチャーは愛馬に「待て」と命令し、大股で宿屋に向かった。
店の前の椅子に、薄汚れた黄色のチュニックを着た大男が腰掛けている。彼は短剣を弄び、近づいてくるウィッチャーを睨みつけた。そして立ち上がり、胸を突き出して告げる。「悪いがもう店じまいだ」
ウィッチャーがそれを無視して進み続けると、男が扉の前に立ちふさがった。「痛い目に遭いてえのか? 店じまいだって――」
ウィッチャーは男の腹に躊躇なく拳を叩きつけた。男は地面に倒れ込み、苦し気にあえぎながら転げ回る。
ウィッチャーはさっと手を出し、男に「待て」と命令し宿屋に入っていった。
中では盗賊もどきの一団がテーブルを囲み、隊商から奪った装飾品類を選別していた。ウィッチャーが入って来ると、ぶつぶつと話し込んでいた彼らは黙り込んだ。そして闖入者に視線を向ける。
「彼らはどこにいる?」ウィッチャーは落ち着き払った様子でたずねた。
虚を突かれて一瞬の間ができた後、ひょろ長い体型の女がテーブルに置いた石弓を掴み取った。
「やめておけ…」
女は弦をピンと張り、大慌てで矢を装填する。ウィッチャーは呆れたように目を上に向けた。「だ… 誰だお前は!?」女がたずねた。
彼は首を鳴らし、剣の柄頭に手を置いた。「彼らはどこにいる?」
女は目を細めて仲間たちに頷いてみせた。それを受け彼らは散開し、ウィッチャーを取り囲む。
「どうする気だ? ここに立てこもって、通りかかる獲物を襲い続けるのか? そんなやり方がいつまで続くと思う? すぐに衛兵を送り込まれて万事休すだ」
「いいや… 連中は街の暴動鎮圧で手いっぱいさ。干ばつのせいで今や無政府状態なんだ。当分はここまで手が回らない。とにかく… さっさと消えな。でないと命はないよ」
ウィッチャーは首を傾げ、聞き耳を立てている。「ふん…」下の方からくぐもった声が聞こえていた。「なぜ彼らを監禁する? 金品を奪って逃がせば、そのほうが簡単だろう?」
「それは――つまり――ええと…」女は目をきょろきょろさせて考え込む。「お――お前には関係ないことだ」そう言って石弓の狙いを定めた。「これが最後の警告だ。本気だぞ」
「悪いことは言わない…」ウィッチャーは剣の柄をぐっと握りしめる。「…もう見切りをつけて家に帰れ」
女は素早く瞬きをした。じっくりと考え、それからゆっくりと、引き金に指をかける。
「よせ…」と言ってウィッチャーは身構える。
女の目が見開かれた――決心がついたのだ。
ウィッチャーは剣を抜いた。
ビン! と弦が弾ける。
そして矢が放たれた。
彼は流れるような一振りを繰り出し、空中の矢を刃の平らな面で捉えた。
カン! と金属音が響く。
矢は軌道を外れて飛び続け、一団のひとりの喉に突き刺さった。男は声にならないあえぎを漏らし、ぶくぶくと血を吐きながら倒れ込む。女が悲鳴をあげた。「ああああ!!」――そして呆然と黙り込み、手から石弓が滑り落ちた。
しばしの沈黙が続いた後、ウィッチャーはしかめっ面で残りの面々を見やった。「まだやるか?」
彼らはすぐさま武器を捨て、両方の手のひらを見せて降伏の意志を示す。皆ぽかんと口を開け、首を横に振っている。みずぼらしい身なりの男が口ごもりながら言った。「ど、どうか、お助けを」
ウィッチャーは平然とした様子で剣を鞘に収める。「行け… 消え失せろ」
一団はウィッチャーに視線を向けたまま、そろそろと正面入口に向かった。外が近づくと一気に駆け出し、互いにぶつかってつまずきながら逃げていった。
ウィッチャーは血の海に浸かった不運な男に目をやると、溜め息をついて悔やむように舌打ちをする。「運が悪かったな…」
彼は部屋の中を調べ、隅のほうに大きな落とし戸を見つけた。
その下から、誰かが声を潜めて言う。「ウィッチャー?」
戸を持ち上げると、木のはしごの下でガランシアが見上げていた。彼女はウィッチャーの姿を見ると微笑み、感謝の気持ちを込めて頷いた。
ウィッチャーは少しだけ彼女をにらみ付け、微かな笑みを浮かべる。「これで二度目だな」
宿屋脇の浅い土手に立ち、ウィッチャーは墓穴を掘るべく地面を掘りだした。ほんの一瞬だけ、彼はアルズールの城を回想した。同胞たちの変わり果てた死体を埋葬した時の記憶だ。魔術師の言葉が頭に響く。「悲しいことだが、やらねばならない。なんとしてもだ!」彼はぎゅっと目を閉じてその記憶を振り払い、目の前の作業を再開した。
そばにはガランシアがいた。オークの木を切り出したベンチに腰掛け、土まみれのウィッチャーを愛おしそうに眺めている。「その人、火葬を望んでたかも…」
ウィッチャーは感心しない目つきでガランシアを睨みつけた。彼女はニヤリと笑う。
「あなたはまさに、白馬の騎士様ね」
ウィッチャーは唸り声をあげてショベルを蹴り、土にめり込ませてもうひと塊を掘りだす。
「フィドルを引っ張り出して… あなたの活躍ぶりを壮大なバラッドにするべきかも」
ウィッチャーは不機嫌そうに息を吐いた。
ガランシアはしばし考えをめぐらせる。「となると、“ウィッチャー”と韻を踏む言葉を考えないといけないわね」彼女はそこで間を置いた。「あるいは…“マドック”と…」
ウィッチャーの動きが止まった。そしてゆっくりと、彼女のほうに首を向ける。
「彼、あなたのことを大事そうに話してた。最後にあった時に聞いたの」
ウィッチャーは墓穴から跳び出してシャベルを地面に投げつけ、威圧的な態度でガランシアに歩み寄る。「今さら俺をどうしようっていうんだ? 俺をつけ回してるのか? お前はなんだ――奴の忠実な犬か?」
「私は誰の手先でもない。私たちが出会ったのは運命の仕業よ。だけど初めて会った瞬間… 私にはあなたが誰なのか分かった」
「たわごとを!」ウィッチャーは大げさに作り笑いをした。「奴らしいな! 何もかも自分の思い通りになると思ってるんだ!」と嘲る。「裏で糸を引いてないと気が済まないんだな!」そして彼は首を鳴らした。「それで? 俺を懐柔するためにお前を送り込んだのか? 立派なお仲間のところに連れ戻そうってか? そんなのお断りだ。あそこは俺の居場所じゃない――今も昔もな。あんなふざけた茶番! 俺はただ殺すだけ――何にもならない殺しを請け負う殺し屋で――それ以上でもそれ以下でもない」
ガランシアは彼が怒るに任せ、しばらくすると首を傾げてみせた。「マドック… どうしてそんなことを言うの? 自分でも嘘だと分かってるでしょ」彼女は微笑んだ。「妄想に取りつかれてるのかも。あるいは真実がまるで見えてないか…」
マドックはなおも怒りを募らせる。「いい加減にしろ…」
彼女の眼が陰を帯びた。「分かってるはずよ。彼は心から――」
「ふざけるな!」
「あなたは彼にとって特別な存在なの。あなたには想像もできない。これだけの時を経ても、最初の――」
「俺は奴のペットでも――オモチャでもない」
「ええ、分かってる――」
「もういいだろう! 放っておいてくれ!」
ガランシアは間を取り、慎重に言葉を選んだ。「確かにあなたの言うとおり、彼は色々なものに諦めをつけなきゃいけない。でもそれはあなたも同じよ」彼女はマドックを見つめ、隣の空いた席を手で叩いた「ほら、座って」
ウィッチャーはしかめっ面を解かず、歯を食いしばって苛立たし気に震えていた。だがやがて観念し、ベンチの端に腰を下ろした。
「ずっと思いつめてるんでしょう?」彼女はじっと答えを待つ。彼は沈黙したが、それ自体が期せずして答えとなった。彼女はおどけた調子で続ける。「ああ、なんて悲しいんだろう! 俺は怪物なんだ、化け物なんだ! ってわけ? 大した悲劇ね!」
その態度に驚き、マドックは彼女を見た。
「メソメソしてないで乗り越えなさいよ」
彼はガランシアを睨みつけ、それから草原のほうへ視線を移した。
「なぜ吟遊詩人をやめたのかって聞かれても、私はいつも誤魔化してる。理由を知りたい?」彼女は返事を待たずに続ける。「語る価値のない話だからよ。もちろん聞く価値もない。引き込まれる冒険譚も、魔法のような展開も、壮大なクライマックスもない。ほとんどの人には受け入れがたい、ごく単純な事実があるだけ。私はそもそも、吟遊詩人になりたいなんて思ったこともなかった。自分で課した義務に過ぎない… 遠い過去の思い出を、ないがしろにしないためにね。私は何十年と続けて、見知らぬ相手の前で歌い続け、あのフィドルを弾き続けた… 惨めで、満たされない日々。罪の意識で前に進んでいた。自分だけが生き延びたってことは… 大きな重荷にもなる。あなたには言うまでもないことね…」
ウィッチャーは聞き取れない何ごとかをボソボソと告げた。
「私はただ、充実した人生を自分から奪ってたの… 自分を罰するという、空虚な理由のために」
「自業自得だな」とウィッチャーは言った。
「ええ、そのとおり。だけどそれに気付くまで、ずいぶんと時間がかかってしまった。過去に未来を支配されてはいけない。亡き者に囚われていては、時間が無駄になる。アルズールだってそう――あれだけの知恵と長寿を持ちながら、いまだにそれを分かっていない。彼は過ぎ去った時に固執している。捨てられない過去に。だけど選択するのは彼自身。あなたも同じよ、マドック」彼女はそこで間を置いた。「あなたの粘土で形を作っているのはアルズールじゃない。もうずいぶんと前からね…」
マドックは沈黙し、考えに耽っていた。
「あなたは地獄を見てきた。私にはその痛みが分かる。本当よ。だけど自分だけが苦しんでるなんて思わないで。それどころか、あなたは恵まれた立場にあるのよ。多くの人は何とか生き延びようと、一日一日をやっとの思いで生きてる。一切の望みを断たれ、そしてあるとき――ポン! と死んでいく。初めから存在すらしなかったみたいにね。でもあなたは違う。私たちのほとんどが夢見ることしかできない場所に行き、色々なことができる。偉業を成し遂げ、世界をより良い場所に変え、人々の記憶に残ることができる。そんな恵まれた立場を、憎悪と頑固さのために台無しにするなんて… 恵まれない者たちへの大変な侮辱よ」
「だから言わせて。アルズールも、彼の夢も知ったことじゃない。死んだ同胞もよ。これはあなたの問題なんだから。自分の運命を自分で切り開いて、より良い未来を作っていくの。手遅れになる前に。だってマドック、あなたはそうできる立場にある」
ウィッチャーは体を前にかがめた。うつろな目で考えに耽っている。
ガランシアが手を伸ばした。手のひらを上に向け、空を見やる。「さっさと穴掘りを済ませたほうが良さそうね」雲一つなかった空にどこからともなく灰色の雲が現れ、小雨が降りはじめていた。「のんびりしてる時間はないみたい」
宿屋の主人が正面扉から飛び出してきた。泥に膝をつき、歓喜した様子で空に手を伸ばしている。「奇跡だ! ああ、神よ!」彼は目を閉じ微笑むと、降りかかる霧雨を一身に浴びた。「あまりに長い苦難の日々だった――」そこで何かに気づき、彼は勢いよく建物の中へ駆け戻る。それから少し経って、ハーフリングとドワーフを従えた彼が再び表に出てきた。その腕には銅の鍋や平鍋がたくさん抱えられている。
容れ物になる様々な道具で懸命に雨水を集めようとする彼らを見て、丘のそばに座っていたマドックとガランシアは共に微笑んだ。
ウィッチャーの視線は空に向けられていた。遠くのある一点から雲が外側に流れており、彼はその様子を注視した。奇妙だ。彼は眉間にしわを寄せた。髭の生えた喉元を掻き、首を左に傾ける。「アルズール…」
「ええ…」しばらくしてガランシアが言った。
彼は考えを振り払い話題を変えた。「それで… 奴はどうやって呪いを解いた? そこをまだ聞いていない」
ガランシアは考え込み、静かに溜め息をつく。「それはまた別の時に話しましょう。楽しく語れる内容じゃないことは確かよ」
ウィッチャーを顔をしかめた。
彼女は優しく微笑んだ。「まともな選択肢が一切残されない時もある。先が見えない中を進み続けて、だけどそれでも選ばなきゃいけない。そして選択には結果が伴う。それがどんなものであろうとね。ウィッチャー、よく覚えておいて。結果から逃げれば、それは積み重なっていく。そして最後には、何らかの形で報いを受けることになる」彼女は旅の仲間たちを見つめた。彼らは宿屋の前で、雨に濡れながら嬉しそうに踊っている。「汚れを被ることなく生きられる者なんてごくわずかよ、マドック。そうできたとしても、若くして死ぬことが多い。私たちにできるのは、せめて最期を迎えるまでに、どうにか天秤のつり合いを取ろうと努力することだけ」
ウィッチャーは鼻を鳴らした。「人生は負債か」
「ええ」
その時、歓喜に沸く声が突然かき消され、耳をつんざく爆音が響いた。
ゴロゴロゴロ…!
カッ!!
まばゆい光が瞬き、辺りが緑と赤に染まる。
マドックはさっと立ち上がり、畑の向うの地平線を見やった。遥か彼方には、雨に濡れたばかりの平原まで届くマリボーの外壁が見える。「何のつもりだ?」
その上空では巨大な雲が不自然に広がり、街の中心から不穏な闇が広がっている。
不意に稲光が瞬き、陰鬱な風景を貫いた。その直後、ゴロゴロと雷鳴が続く。さっきまでの小雨は土砂降りに変わり、そよ風は荒ぶる強風と化していた。遠くの空で灰色がかった黒雲が渦を巻き、その中心にあいた穴が徐々に広がっていく。脈動する光の亀裂がそこから発生し、葉脈状に伸びながら様々な色を発し、地平線を鮮やかに染め上げていく。
ガランシアとマドックは、交差路に集まっていた旅人たちに加わった。彼らは皆、彼方で巻き起こる混沌を見つめている。
「ああ、嘘だろ…」ハーフリングがひとり呟いた。「なんてことだ」
「〈門〉だ!」打ち付ける豪雨に負けじとドワーフが叫んだ。「エランダーと同じだ!」
「こ、こいつは大変だ!」兵士は驚愕し、青ざめた顔で目を見開いている。「あり得ない…」
渦巻く嵐の内側で、おぞましい何かが〈門〉から這い下りてきた。細長い巨体の両側に、かぎ状に曲がった手足が並んでいる。それが身をよじり、マリボーの上空に舞い降りてくる。
恐ろしい怪物が都市に衝突し、大地が震えだした。
その背後で空にあいた大穴が急激に閉じ、放たれていた色鮮やかな光も消え去る。残されたのは黒雲と、黒く染まった景色、そして、チカチカと断続的な光に照らし出される怪物の巨影。光が瞬くたび、街を破壊する大きなムカデ状の巨躯が垣間見える。怪物は勢いよく食らいつき、突き出した塔に長い胸部を巻きつけ、建物を瓦礫に変えていく。
クソ、なんてこった。マドックは考えた。
雨に目を細め、ガランシアの方を見やる。彼女の茶色い大きな瞳が柔らかく、そして粛々と訴えていた。「行って」と、口の形だけで告げる。「彼が助けを必要としてる… 私たちみんなも」
マドックはためらうことなく動き出し、馬を繋いでいた柱まで行って鞍に跳び乗った。手綱を握りしめ、彼が助けた者たちの方をもう一度だけ見る。ハーフリングは片手鍋で必死に雨から身を守り、ドワーフは何ごとかを叫んでいたが、打ち付ける雨音で聞き取れない。兵士は宿屋の主人につかまってバランスを取りつつ、嘆かわし気に首を振っている。そしてガランシアは、悲嘆に暮れた目に恐怖を滲ませながらも、希望を託してウィッチャーに微笑み、理解を示し頷いてみせた。
マドックも頷き返し、馬を向き直らせる。暗い道に向かって拍車を掛け、マリボーへと駆け出した。広がる漆黒と稲光に向かって。全てを呑み込み、惨劇を繰り広げる怪物に向かって。破壊と死と混沌の化身に向かって。
彼は自身の創造主のもとへと進む。
己の運命が待ち受ける先に。