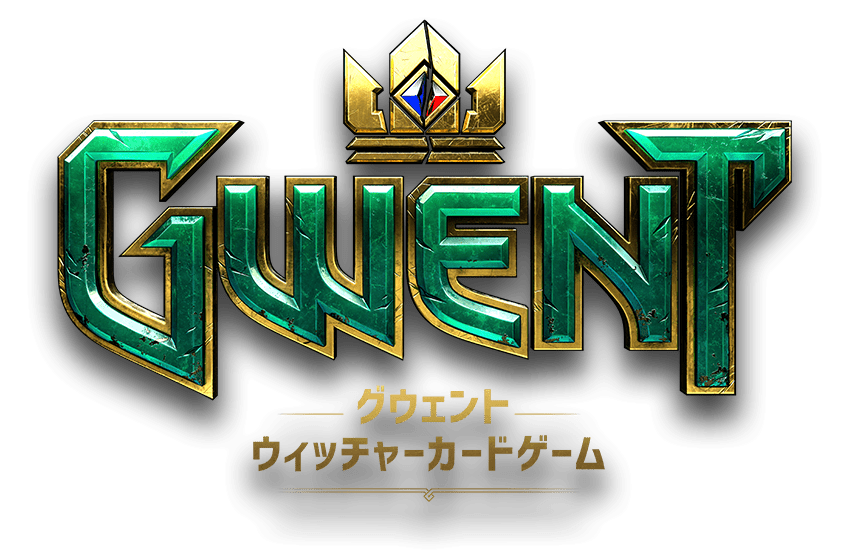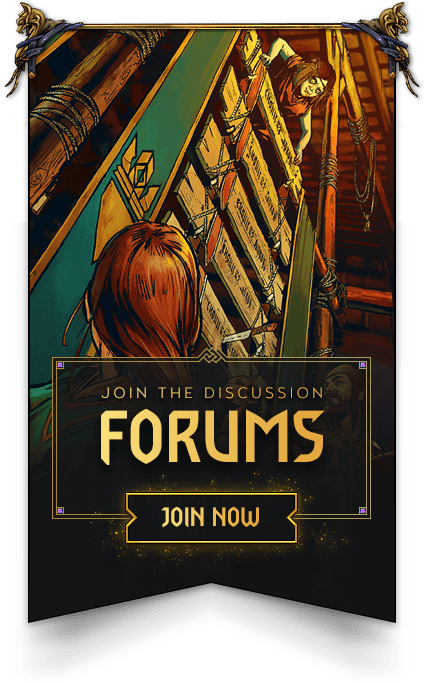仮設病院は死の匂いに満ちていた。
「血が要るだろ、レジス」
「時間があればいい」
「彼らはどうせ死ぬ」
「私は殺さない」
足元には霜で固まった血まみれの包帯が散乱し、踏みつけるとバリバリと音を立てた。掃除をする者も、火に燃料を入れる者もいないのだ。
「お前の考えは理解できん」デトラフの声に苛立ちがこもる。
「だとしても私の決断を尊重してくれ」
「お前の頑固さは私にとっても危険なんだ。弱った状態で足を引っ張っている」
「倫理的問題はさておき」とレジスは語る。「こんなことになったのは、生まれ持ったお前の習性にそもそもの原因がある。我々は注意を引いてしまった。干からびた死体の跡を残せば居場所を知らせるようなものだろう。しばらくは私に従ってもらう」
「ならどうするんだ?」
「正体を隠して紛れ込もう」
「人間に扮して? 屈辱的だな」デトラフは不安げに体を動かし、マントの下の傷に手を触れ、短く苦痛の声をあげた。
「化膿するぞ」とレジスは指摘する。
「一体どういうことだ? 傷が閉じない。変身しようとすると傷口が広がっていく。ただの人間になぜこんな真似が…」
「違う。あれは人間でなくウィッチャーだ」
デトラフは思わず連れの顔を見た。その眼差しに浮かぶのは煩わしさと、それを上回る好奇心だ。
「殺しに特化した変異者。異界の来訪者からこの世界を守る集団だ」とレジスは説明する。
「我々からか…」
「ああ、我々も含まれる。幾世紀もの歴史を持ち、敵とみなす存在に関して膨大な知識を蓄えている。その点は身をもって体感しただろう。
警戒すべき相手だ」
その言葉に考えをめぐらせていると、デトラフの顎の筋肉がひくついた。そしてようやく、「お前に任せる」と告げた。
そこでテントが音をたてた。吸血鬼たちは瞬時に入口を見やる。メリテレの信者が疲れ切った笑みを浮かべていた。「何なりとご用命を。お待たせして申し訳ありませんでした。なにぶん一人なもので。他の者たちは軍と共にヴィジマへ向かいました」
「負傷者を置き去りにして?」レジスは驚いた声を上げる。「なにをそこまで急ぐ? 戦争はもう終わった。ニルフガード軍はブレンナで敗北したんだぞ」
信者は俯いた。「クラウンの支払いが滞っていたのです。6ヶ月も。軍は反乱を匂わせて、大元帥殿に首都へ連れていくよう迫ったのです。未払いのクラウンを直に回収するために。ですが私は診療所の仕事に志願しました。奉仕を誓った以上、どれだけ厳しい状況であろうと務めを果たさねばなりません」
「この病院は物資もろくにない状態だ」
「大元帥殿は寛大にもご自身のテントを提供してくださいました。このテントがそうです。そしてご自身の負担で食糧と医療品を購入し、こちらへ送ると約束してくださいました。わずかですがお2人にも軽食をご用意しましょう。お召し上がりになりますか?」
「ありがとう」とレジスは笑い、唇をすぼめた。「だが遠慮しておこう。その代わりに教えてほしいんだが、善良な旅人がここを通りかかったりしなかったか? 私たちだけでこの先を進むには物騒だと思ってね。この頃は危険な連中がわんさとうろついている…」
「朝方に3人の兵士が来て負傷者の1人を連れて行きました。彼らの指揮官だとかで。西へ向かいましたよ。迎えが来てよかったです。不運な方がまた1人、救われたのですから」
「そうか、ありがとう」
やがて彼らは仮設病院を後にした。西へ延びる道には傷のついたニレの木が並んでいる。
「誰も助けに来はしない」とデトラフが言った。「彼らは忘れ去られる。それが人間だ。記憶力が乏しい」
「だが彼女は残った」とレジス。
彼らの頭上では、鴉たちがテントの周囲を飛び交っていた。
雪は降りやんでいた。
アースキンは目を擦り、たそがれに沈みゆくソドゥンの野原を真っすぐに見据える。この辺りで足を止めるべきだ。彼はそう判断し、道を離れて近くのくぼ地へ向かうと連れの2人に合図した。
ネリスが背中の荷物を降ろして毛布と食糧を取り出し、オシアンが火を起こした。アースキンはそりの綱を離して腰を下ろし、自分の手をほぐし始める。
「すぐ手伝うから少し待ってくれ」と彼は言った。
ネリスはそりに横たわった男に視線を向ける。「休んでおきなよ。休めるうちに」
「兵士長め」オシアンが指に息を吐きかけながらぼやく。「ぶくぶく太りやがって。こいつがもう少し軽かったら今ごろアイナ川を越えてるはずだ」
「ついてないね」とネリス。
アースキンは包帯を巻かれた兵士長の上に身をかがめ、浅い呼吸に耳を澄ました。「苦難を共に乗り越えるしかない」と彼は言った。「最初の見張り番は俺がやろう」
*
盗んだワインはショウガの味がして、アースキンは思わず顔をしかめた。そして毛布を肩に巻き、眠っている仲間たちを見やった。オシアンは自分の息子でもおかしくない年齢だ。彼がテメリア軍に入隊して間もなく黒の軍団の侵攻が始まった。2人はジョン・ナタリスの指揮下でディリンゲンを懸けて共に戦い、ソドゥン解放時にはフォルテスト王の下で戦った。ネリスは自由軍の傭兵だ。ライリアの男爵の娘だと言っているが、アースキンはその話を信じていない。それが事実なら、こんな旅に巻き込まれて凍死しかけているはずがないと思ったからだ。
なんという旅だろう。アースキンは溜め息をついてワインに口をつけた。事の発端は兵士長が語ったある宝箱についての話だ。がれきの散乱する地下室にあるというその宝箱の話を聞き、全員で決断をした。後戻りなしの一線を越えたのだ。
たき火の暖かさがアースキンの眠気を誘った。彼はあくびをして立ち上がり、ブーツの先でネリスをつつく。「お前の番だ」と告げ、ワインボトルを彼女に手渡す。ネリスは目をこすりながらワインをひと口飲むと、火に向かって吹き出した。ショウガの味だ、と言いかけて彼はネリスが背後の暗闇を見つめていることに気付き口をつぐんだ。
「怖がらなくていい」と闇の向こうから何者かが告げた。
少し間があって、見知らぬ男2人が明かりの届く範囲に進み出る。「武器は持っていない」と灰色の髪をしたほうが言った。さっき聞こえたのと同じ声だ。
「我々はディリンゲンに向かっている。なにかと物騒な時代だからな、できるだけ大人数で旅をするのが賢明だとは思わないか? 目的地が同じならなおさらだ」
「なぜ目的地が同じだと?」オシアンが訪ねた。彼は身をかがめ、既に背中で短剣を抜いている。
「余計なお世話よ」とネリス。
アースキンは黙ったまま状況を見極めようとしていた。2人の闖入者に危険そうなところはない。まず第一に、本人の言葉どおり武器は持っていないように見えた。そして第二に、彼らは具合が悪そうだった。少なくとも衰弱している。灰色の髪をしたほうは死人のように青白い顔で、声にも覇気がない。もう片方の黒髪の男は沈黙し、わずかに前かがみの姿勢で腰の辺りに手を当てている。怪我をしているのかもしれない。
灰色の髪の男が顎でそりを指した。「あの男は一週間と持たない」と彼は言う。「だが幸い、私は医者だ。ディリンゲンに避難所を持っている。急いで向かえば彼を助けられるかもしれない」
風が辺りの木々を揺らし、消えかけた火を燃え立たせた。
そこでアースキンは、ネリスとオシアンが自分の返事を待っていることに気付く。彼は考えた。もし目的地へ着く前に兵士長が死んでしまったら、全てが無駄になる。となれば医者は頼もしい存在だ…
彼は剣の柄から手を離し、低くうなり声をあげて頷いた。「あんたら、名前は?」
*
夜明けには出発の準備が整っていた。アースキンは足で灰を払いつつ、新たな旅の仲間たちを観察する。灰色の髪のレジスは嘘をついていなかった。立っているのもやっとという状態だが、彼は手際よく兵士長の包帯を付け替え、傷用のあて布を用意したのだ。そして驚いたことに、もう片方のデトラフはそりを引くと申し出てきた。
そして彼らは出発した。デトラフは数歩進むたびに立ち止まり、痛みに顔をしかめている。レジスが片手を添え、そんな彼を押さえている。アースキンは背嚢の位置を調整して2人のところまで歩み寄った。
「ずいぶん疲弊してるようだが、誰にやられたんだ?」と彼はたずねた。2人から返事はない。デトラフは追っ手を警戒するかのように背後を振り返っている。アースキンはそれ以上追求しなかった。どういうわけか、もうその答えを知りたいとは思わなかったのだ。
「おぞましき化け物が鐘楼に巣を作ったのだ、ウィッチャー。奴は夜になると街へ飛び立ち、人をさらっては巣に運んで犠牲者を貪り食っている。実に恐ろしい事態だ! あの化け物を始末してくれ。いくら出せばいい?」
「200オレンだ、議員さん。その化け物は吸血鬼さ。簡単に済む相手じゃない」
議員は彼の言葉に感心していた。「化け物の正体がもう分かったのか?」
「死体を調べたからな」
実のところ、その化け物はソレンセンがずっと追っていた標的の怪物なのだが、説明は省くことにした。彼は議員よりずっと大物の依頼者から仕事を引き受け、手がかりを辿ってこのウォーファートまで来ていたのだ。同じ仕事で2度報酬を貰えるなら、わざわざそれを断る道理はない。
議員は考え込み、そして首を振った。「しかし高すぎる」
「なら自分たちでどうにかするといい」
「やってはみたさ。勇ましい城の衛兵たちが躍起になって退治を試みたが、彼らの剣はあの化け物に歯が立たなかったのだ。いっそ鐘楼を焼き払って奴を追い出したいところだが…」
「ならぬ!」そう叫んだのは、それまで聖堂のステンドグラス越しに鐘楼を見つめていた総主教だった。「聖なる場所に火を放つなど言語道断! 聖堂参事会が3000オレンもかけた鐘楼だぞ! 焼き払うなどあり得ん!」
「恐ろしくはないのですか?」と議員が苛立たしげに告げる。「あの化け物の近くでそんな大声をあげて」
「ここは聖歌に守られておるからな」総主教は怒りをあらわに唾を吐き捨てた。「この歌が続く限り魔術の力は届かん」
聖歌隊が身廊に並び、歌い続けていた。単調な歌声は厳かな聖堂の壁に香料のように染み込んでいく。だがそこで、ソレンセンにある考えが浮かんだ。「主教殿」と彼は頭を下げる。「信仰と聖歌は吸血鬼に抗う最良の手段です。可能であれば聖歌隊をお借りできないでしょうか? 祈りで奴の感覚を惑わせ、力を奪うのです。その隙に私が致命傷を負わせます」
総主教は得意げに議員のほうを見た。「ああ、もちろん構わんよ」
*
おとりは十分に役目を果たした。漆黒の空から吸血鬼が襲い掛かり、聖歌は恐怖の叫びと化していた。目のない頭、コウモリの翼、滑らかな皮膚の下で脈打つ血管。ガラシャム族だ。
吸血鬼はそばにいた聖歌隊員を掴むと、その体に牙を食い込ませた。同時に、鋭い爪のある長い足でもう1人を地面に押さえつける。
捕食時の圧倒的な高揚感は吸血鬼の感覚を鈍らせ覇気を奪う。攻撃するには絶好の機会だ。ソレンセンはガーゴイルの石像裏から飛び出し、円盤投げの要領で攻撃を繰り出した。鎖が宙を舞う。吸血鬼の手足に鎖が絡み付き、銀が皮膚に食い込み音を立てた。ガラシャム族は聖堂の傾いた天井を転げ落ち、下を通る石畳の道に倒れ込んだ。その体に崩れたタイルが次々と降りかかる。ウィッチャーは吸血鬼を追いかけ、排水路へとたどり着く。とどめの時だ。彼は銀の剣を抜き、鎖を解こうともだえる吸血鬼の首に切りかかった。
だがその瞬間、コウモリの体が大きな血しぶきと化す。剣は石にぶつかって音を立て、鎖がその場に落ちた。拘束を解かれた吸血鬼は再び肉体を出現させ、耳をつんざく叫びと共に翼を広げて宙に浮かんだ。ソレンセンは猛烈な突進を跳び退いてかわし、体を回転させて跪く姿勢を取った。開閉式の弓がカチッと音を立てて展開し、彼は狙いを定める。そして発射。矢を受けた吸血鬼は空中でよろめき、苦しげに空へ飛び立ったものの鐘楼に墜落して轟音を響かせた。
狩人はなおも獲物を追う。ソレンセンは石工が残していった昇降機の綱を掴み、剣で重りを切り落とした。落下するレンガの勢いが彼の体を持ち上げ、一瞬で最上階まで舞い上がる。
だがそこから見えたのは、月に浮かぶコウモリの影が西へ飛び去っていく姿だった。彼は怒りの声をあげた。
薬草と乾燥肉の香りが風に運ばれてきた。レジスが立ち止まって告げる。「近くに人がいるぞ」
デトラフも無言で同意する。
一行はヤルーガ河沿いを何日も歩き続けていた。人間の同行者たちは未だ2人のことを警戒しており、言葉を交わすこともほとんどない。吸血鬼たちはそんな彼らと距離を取り、数歩後ろを進んでいた。
「興味深い連中を見つけたものだ」とデトラフが告げる。「あの女司祭は兵士だと言っていたが、恐怖と欺瞞の臭いがぷんぷんする」
「脱走兵だな」
「どうして分かる?」
「推測だ。あの負傷した男… ジャケットの紋章が外されていた」
「なら我々は惨めな逃亡者集団に加わって人間に溶け込むと? 傑作だな」
「決めつけるのはまだ早い。ありがちな言い方になるが、人間と暮らすとこの世に単純なことなどないと思い知る。我々には彼らの素性も、なぜ逃げているのかも、誰から逃げているかも分からない。彼らのことはまだ何も知らないに等しい」
オシアンの呼びかけで2人は足を止めた。彼は手を振り、近くの農場を指さしている。森の端にある小さな農場だ。柵のそばに使い古された馬車があり、厩舎から馬のいななきが聞こえる。煙をあげる煙突が暖炉の存在を示し、彼らを誘っていた。吸血鬼たちは同行者の様子を観察する。彼らは話し合い、やがて建物のほうへ歩き出した。
「確かに彼らのことはまだ何も知らない」とデトラフ。「だがそれも変わりそうだ」
*
農民は酒樽を抱えて戻ってきた。彼はそれをテーブルに置き、粘土のカップに酒を注ぐ。部屋にビールの香りが漂いだす。「どうも話が飲み込めないな」と彼は言った。
アースキンは勢いよく酒を飲み、口ひげに付いた泡をぬぐった。そしてテーブルに置かれたユリのパッチを指で叩く。「さっき説明したとおりさ。俺たちは秘密任務に就いてるテメリア軍の者だ。ニルフガード軍から取り戻した、ええ… 捕虜をだな、運ばなきゃならない。早急にアイナ川を越えるために馬車が必要なんだ」
「それに馬2頭も」とオシアン。
ネリスは扉のそばで壁に寄りかかっていた。抜き身の剣を片手に、床板の隙間をつついている。「食べ物もね」と彼女が付け加えた。
「それは困る。こんな僻地で馬車を失ったら、俺たちが冬を越せなくなる」
「俺たち?」オシアンが反応した。「他に誰かいるのか?」
農民は扉のほうをちらりと見る。オシアンが唾を吐き、短剣を抜いてテーブルに置く。暖炉の火が刃の中で揺らめいていた。
「ああ、命だけは…」
「残念だが俺たちに慈悲を求めても無駄だな」
「オシアン…」とネリスが口を挟んだ。
「黙ってろ。全てはこいつ次第だ」
そこで暗がりに佇んでいたデトラフが彼らに近づき、テーブルの上に小袋を投げ置いた。コインのぶつかる音が響く。「好きにしろ」と彼は告げる。「私は散歩をしてくる」
扉が勢いよく閉められると、今度はレジスが小袋を持ち上げ農民に迫った。「私の連れは兵士だ。盗っ人ではない」と語り、オシアンの目をじっと見つめる。「雌馬1頭でいい。そりを引かせるにはそれで足りる。そして… 謝礼は十分支払う」
アースキンは口を開けたまま言葉を失っていた。
吸血鬼は微笑みかける。「テメリア兵は決して人の物を奪ったりしない。もしそんなことをしたら、秘密任務のことがあらぬ相手にまで伝わってしまう危険もある。そうなればもちろん… 窮地に立たされるのは彼ら自身だからな」
*
エインはブーツの底の感触で枝を探していた。
雪を散らして拾い上げ、枝をバスケットに放り込む。もう十分だろうと判断し、彼女は家に帰ることにする。
足早に進みつつ、彼女はお気に入りの歌を小さくハミングする。だが森の終わりまで来たところで、バスケットを落として素早く後ずさった。彼女は木の裏に隠れて長いあいだ待ち、それからゆっくりと顔を出してみる。
小屋に見知らぬ集団の姿があった。ルドカが女に手綱を引かれ、息を荒げて忙しなく脚をばたつかせている。食料庫から2人の男が現れ、袋と酒樽を運び出している。そして年かさの4人目が、小屋で彼女の父親と話をしている。
エインはさらにもう1人の気配を感じた。他よりもずっと近くに。
「ここでじっとしていろ」と背後から声がする。低く魅惑的な声だ。
「でもお父さんが…」
謎の人物は彼女の肩に手を置いた。その手は冷たくて青白く、手のひらに赤い血の文様がある。「心配しなくていい。彼らはすぐにいなくなる。見ろ。じっくり観察するんだ。単純なことなど何もないこの世界を」
「何を言ってるの?」
「気にするな」
エインは黙っていた。灰色の髪の男が小袋から何か取り出し、父親に渡している。黄金のきらめきが見えた。
「連れていくのはルドカだけ?」しばらくして彼女はたずねた。
「ああ。私の友人には説得の才能があってね」
「よかった」
「よかった? とんでもない幸運だったんだぞ。根こそぎ奪われるところだったんだからな」
エインは振り返って男の目を見つめた。「でも見守ってくださる方がいたのね」
アイナ川は沈みゆく日の光を受けて輝いていた。
川のそばにはヴィドルト要塞とカルカノ要塞がそびえ立っている。戦火で焼け落ちたものの、テメリア軍の手でゆっくりと再建が進んでいるところだ。
オシアンが北を指して告げる。
「あれを見ろ。氷で岸が繋がってる。あそこを渡ろう」
アースキンは指の隙間から鼻息をもらした。「どうだろうな。氷は所々薄くなってるし穴だらけだ。おまけに要塞も近くにある。アイナ川とトラヴァ川の合流点まで進んだほうがいい。人目につかない浅瀬を探そう。兵士長にとってもそのほうが安全だ」
「同行者として言わせてもらうが」とレジスが口を開く。「本当に彼のためを思うなら急いだほうがいい。一番賢明なのはカルカノで助けを求めることだ。おそらく医療物資も揃っているからな。だが見たところ、あまり気が進まないようだな?」
「ああ、そのとおりさ」とアースキンが応じる。「よく分かってるじゃないか」
デトラフが微笑んで告げる。「一体どうなってる? 同じテメリア軍だろう。なぜ助けを求めない?」
「いいか、よく聞け」とオシアン。「俺たちがあんたらの素性をたずねたか? どこから来て、誰にぶちのめされてそんな死人みたいな有り様になったのか詮索したか?」
デトラフは何も言い返さない。
「ならばフェン・カーンへ向かおう」とレジスが言った。「あそこに以前、避暑用の別荘を持っていてね。物資がいくらか残っているかもしれない」
「お医者さん、あんた正気か?」とアースキンがたずねる。「あそこは忌まわしいエルフの土地だぞ。彼のためを思うなら、なんてよくも言えたもんだ! やっぱりアイナ川を渡るしかない。ここでな。それからディリンゲンへ急ぐ」
*
彼らは暗雲に乗じ、凍った川に足を踏み入れた。静寂を破るものは氷の砕ける音以外に何もない。
そして気付かれずに渡りきれるかと思ったその時、彼らの背後で物音がした。
オシアンが忌々しげに告げる。「武装した騎手が3人。巡回だ」
巡回兵たちはすぐに彼らに気付いた。1人が馬を走らせ、全速力で要塞へ向かう。あとの2人は岸辺まで行って馬を降り、剣を抜いて氷上を進み始めた。「止まれ! 止まるんだ!」と彼らは叫ぶ。
そりを引いていた雌馬はその言葉に従った。
「止まるな、この老いぼれ!」アースキンが叫び、手綱を勢いよく引いたが効果はなかった。テメリアの巡回兵はすぐに彼らの近くまで迫り、互いの顔が見える距離になっていた。
レジスがデトラフのほうを見る。「交渉してみよう」
だがそこでオシアンが唾を吐き、パチンコを構えた。
投石が風を切り、片方の兜に命中する。兵士はうなり声をあげて氷上に倒れ込んだ。続いてもう片方の兵士がそばにいたネリスに飛びかかり、取っ組み合いの末にバランスを崩し、2人は氷の裂け目に落下した。
「ネリス!」アースキンは手綱を捨てて裂け目に駆け寄ろうとする。
オシアンがその腕を掴んで叫ぶ。「よせ! 早く逃げるんだ!」
レジスに逃げるつもりはなかった。彼は淀んだ水中へと飛び込み、ネリスの姿を捉える。彼女とテメリア兵はもみ合いながら沈んでいく。兵士の鎧が重しになり、2人を川底へ引き込んでいるのだ。ネリスは足をばたつかせ、口から空気を吐き出している。レジスは2人のもとまで下降してその体を引き上げようとしたが、再生したての体は思っていたほどの力を出すことができなかった。力を込めると肩の関節が外れるのを感じた。歯を食いしばり、骨が砕けて激痛が走り、その体は限界に追い込まれていく。
そこでデトラフが水に飛び込んだ。
彼はレジスを押しのけ、片手でネリスを、もう片方の手でテメリア兵を掴むと2人を引き離して素早く水面に上昇していった。
*
彼らがアイナ川の岸までたどり着いた時、アースキンとオシアンは姿を消していた。川沿いの要塞では警報が鳴り響いている。レジスはネリスのことを支え起こそうとしたが、彼女はそれを断って可能な限りの速度で森のほうへ歩き出した。彼は素早く後に続き、振り返ってデトラフの様子を確認する。テメリア兵の体を引きずっている姿が見えた後、レジスの視界は木々に遮られた。
彼らは長いあいだ森を走り続けたが、やがて限界に達し、フェン・カーンの丘の合間を歩いて進んでいた。ネリスはこの土地にまつわる不吉な話を聞いていたが、もはや抗議する体力も残っていない。
やがて2人は簡素な小屋にたどり着いた。テーブルに瓶が並び、壁には乾燥させた薬草が掛けてあった。それらの香りがネリスの嗅覚をかき乱す。
レジスはどこからか乾いた洋服を引っ張り出し、彼女が着替えている間にテーブルの瓶から何かを探していた。
「あんたの小屋なの?」と彼女はたずねた。
「そうだ」と彼は応え、肩をさすりながら痛みに顔をしかめる。「よし、あったぞ」
彼らは外へ出て焚き火のそばに腰掛けた。レジスが火を起こし、フラスコについた埃とクモの巣を払ってコルクを抜き、それをネリスに手渡した。
彼女はそれを飲んだ。アルコールが喉を刺激し、彼女の体を温める。
「すごい… 何なのこれ?」
「マンドラゴラの自家製酒だ」
「あんたも飲む?」
「お構いなく。禁欲主義でね」
「禁欲主義のくせに密造酒を作り、川に沈んだ赤の他人を命懸けで助ける。不思議な奴ね、レジス」
「ふん… 以前、“どうしようもない利他主義者”のドワーフに会ったことがある。それと近いものだろうな」
2人はそのまま沈黙した。ネリスは彼の背後で雪にちらつく影を見つめていた。何かがおかしい。そして違和感の正体に気付く。身が強張り、小さなうめき声がもれた。「あんた、影が… ってことは…」
「ああ、そうだ」
彼女は素早く身を引き、自分の首元を手で覆う。
レジスは残り火に木を足した。「怯えなくていい。言ったろう、私は禁欲主義者だ。そもそも危害を加えるつもりなら助けたりしない」
「デトラフも?」
「デトラフもだ。だが黙っておいたほうがいいぞ」
炎が爆ぜて音を立てる。まるで召喚されたかのように、闇の向こうからデトラフが姿を現し2人の間に腰を下ろした。
「テメリア兵は無事だ」と彼は告げる。「見つかりやすいよう城壁のそばまで運んでおいた」
ネリスの体は震えている。頭の中は混乱状態だ。レジスに借りた服が肌をひりつかせ、大きさの合わないズボンが腰からずり落ちる。彼女はそれを引き上げ、ベルトを目一杯きつく締めた。
「どうかしたのか?」とデトラフがたずねる。
彼女は一瞬だけ躊躇し、そして決断した。
酒を飲み込み、微笑んでみせる。
「別に。すべて平常よ」
議員は息を切らせて塔を駆け上がった。事前に警告されていたため、香水を染み込ませたハンカチを鼻にあてて身構える。現場ではソレンセンが既に調査を開始していた。吸血鬼の巣には腐敗度合いの様々な死体がいくつも転がっていたが、彼はその臭気も意に介さないようだ。
「馬のそばに報酬を用意しておいたぞ、ウィッチャー。総主教がさっさと街から出て行くようせっついている」
ウィッチャーは肩をすくめてみせた。彼は死体についた牙の跡の間隔を計っている。「妙だな。歯形が2種類ある。ガラシャム族は犠牲者をここまで運び、抵抗できないよう脊椎を折っていたようだ。親鳥が虫を噛み潰して雛に与えるようにな」
議員は眉をひそめた。「つまりどういうことだ?」
「奴は他の誰かに餌を与えていたんだ」
*
「サブリナ」
またしても返事はなかった。ゼノヴォクスは沈黙を貫いている。ソレンセンはいっそこの会話装置を川に投げ捨てたい気持ちだったが、答えを聞かないわけにはいかなかった。好奇心が苛立ちに勝り、彼はもう一度会話を試みる。
「サブリナ、この馬鹿女め」
「あら、ソレンセン。ずいぶん礼儀正しいのね」装置から金属的な声が響いた。馬が不安げに聞き耳を立て、速度をゆるめる。ウィッチャーはそんな牡馬に拍車をかける。
「嘘をついてくれたな」
「なんのこと?」
「吸血鬼は2人いる。報酬も2倍にしてもらおうか」
「そんなことのために連絡してきたの? 金額交渉のために?」
「標的の素性を知りたい。どんな状況で逃亡したのかも教えてくれ」
「質問はなし。そういう話だったでしょう?」
「危険性が増したんだ。相手のことを知る必要がある。それでも話さないというならアングレンに帰らせてもらう」
そして長い沈黙が流れた。ソレンセンはゼノヴォクスがまた調子を悪くしたのかと思いかけた。
「私と仲間の女魔術師2人は、背教の魔術師ヴィルジフォルツが根城にしてるスティガ城の襲撃を命じられたの。そこで私たちはあの化け物の死体を発見した。呪文で殺された状態でね。私たちはその再生を試み、成功した」
「吸血鬼を蘇生したのか? 一体なんのために?」
「聞きたいことがあったのよ。重要な情報を握ってる可能性があった。スティガ城では未だに全容の分からない大きな出来事が起こってるから」
「さぞ和やかな対話ができたんだろうな」
「そうはならなかった。彼は人間に対してエミエル・レジスと名乗ってる。遠い昔から生き、教養と洗練を身に着けた存在であることはいくつもの証拠で示唆されてた。だけど目覚めた時の彼は、飢えに支配されて自分を見失っていた。それで、まともに話を聞く間もなく逃げられてしまったの。私は彼の力を見くびっていた」
「あるいは誰かの助けがあったんじゃないか。さっきも言ったとおり、吸血鬼は2人いる。一緒に行動しているはずだ」
「依頼を引き受けたことを後悔してる? それともまだ報酬をつり上げる気?」
ソレンセンは彼女を無視した。角を曲がったところで古ぼけた小屋が見えてきた。彼は手綱を引き、馬をそこへ向かわせる。
「話はここまでだ。仕事をしてこよう」
「ええ、頼んだわよ」
*
「テメリアの略奪者さ。ケチな盗っ人どもが俺たちから盗もうとしてきたんだ。でも灰色の髪の男が奴らを止めてくれた。声を荒げることもなく、連中をなだめたんだ。おかげで食料を根こそぎ持ってかれずに済んだ。おまけに馬代も払ってくれた」
「金貨よ…」と言ってエインは俯いた。考えるより先に言葉が出てしまったようだ。
ウィッチャーは首の傷を触りながら言った。「それを見せてくれ」
農民は娘を睨みつけた。新たな訪問者は馬に大量の武器を積んでいる。そして蛇やトカゲを思わせるあの目つき。おとなしく従っておくべき相手なのは明らかだ。彼は諦めて木靴を脱ぎ、ナイフで靴底を開いてコインを取り出した。
色あせた金貨には、有翼の獅子に人間の頭がついた生き物が描かれていた。裏面には戦車の紋様。ソレンセンは同じコインを前にも見たことがあった。ドゥア・ルガル・イディンの墳墓で。彼の顔に狼の笑みが浮かぶ。もはや手がかりは絶えたかと思っていたのだ。
「このコインは300年以上前のものだ。今では古代の墓でしか見つからない。とんだ幸運だったな… 連中に見逃してもらえて」
「あいつは墓荒らしだったのか? ハイエナめ」
ソレンセンは馬の腹帯を調整し、あぶみに足を乗せると鞍に跳び乗った。「墓荒らしなんてもんじゃない。その時代を実際に生きた奴だ」
農民は金貨が持ち去られるのを黙って見届けた。ゴクリと唾を飲み、溜め息をつき、薪小屋に閉じこもっている娘をなだめに向かった。もはや怒る気などなくなっていた。
ネリスは吹きすさぶ風から目を覆いながらレジスに追いついた。
「ディリンゲンに隠れ家があるって言ってたけど、そこに向かってるの?」
「そうだ」
「どうして?」
「隠れるんだ。ウィッチャーに追われてる。怪物狩りだ」
一行がフェン・カーンを出てヤルーガ河に戻ったのは2日前のことだった。空がようやく晴れ、雪に覆われた平野が夕日に照らされて輝いている。
「ウィッチャー? そんなの、5人束になってもあんたみたいな存在には敵わないんじゃない?」
デトラフは外套のボタンを外し、彼女に腰を見せた。
「見ろ」
彼の脇腹がひどくえぐれている。傷を見たネリスは歯の間から息を漏らす。
「3週間前、ウォーファートで奴に襲われた。普段なら一晩で治る傷だ」
「吸血鬼狩りの専門家のようだな」
レジスが口を開く。
「用心しなければ」
「用心するならフェン・カーンにいればよかったじゃない。あそこなら誰も近寄らない…」
「迷信と石ころだけでは足りない」
デトラフは反論する。
「我々にとって安息の地として機能するように作られた場所があるんだ」
ネリスは指の関節を鳴らした。
「少し、手を貸してほしいことがあるの。ディリンゲンの近くに…」
人の声が聞こえ、彼女は口をつぐんだ。レジスが枯れた木々の合間に作られた野営地を指差した。並んだテントには穴が空き、中の炎から煙が立ち上っている。
「その話は後だ」
*
「戦争の終わりに差し掛かると、連中は私たちを故郷から追い出し、まだ居座っているのよ。兵士なんか… 地獄に落ちればいい」
そう訴える女性の後ろに広がる難民の野営地を、一行は無表情で見つめていた。
「あいつらは私たちの村に旗を掲げ、駐屯地のように扱っているわ。私言ったの。ここは私の故郷で、そこに繋ぎとめてあるのは父や祖父がヤルーガを行き来するのに使った船なのよ、って。でも全然聞いてくれなかった。子供を抱えて懇願したわ。冬の寒さは厳しいし、食料もない。小屋1つでもいいから返して、人間でしょ、って」
「聞く耳を持たずか」デトラフが返答する。
女性の影に隠れていた子供が顔を出した。腹をすかせているようで、一行を希望に満ちた目で見つめている。女性は子供の髪を顔から払い、彼のフードを整えてやった。
「彼らはニルフガード人を侵入者と呼んでいた。侵略者ですって。黒の軍団との戦いが終わったから、この国は解放されたんでしょう? 自分たちの小屋に戻れないなんておかしいわ。まるでこっちが負けたみたいじゃない」
レジスは歯を食いしばった。
「明日まで待っていなさい。夜明けには家に帰れるから」
「でも、軍が… 私たちも立ち向かったのよ」
「分かっている。今度は私に任せてもらいたい」
*
集落に到着した頃には夕暮れ時になっていた。積雪によって屋根が崩れた小屋が5つ、桟橋が1つ、そして釣り船のマストが穏やかに揺れていた。一番大きな小屋から、笑い声と楽しそうな叫び声が聞こえてくる。
レジスは肩から鞄を下ろしてデトラフに渡した。
「ここで待っていろ」
ドアを押し開けると音が鳴った。室内はパイプの煙が充満し空気がこもっている。テーブルを囲んでいた兵士たちはレジスを見ると静まり返った。
こめかみに傷があり髭を蓄えた男が素性を尋ねる。
「エミエル・レジスだ。ディリンゲンに向かっている」
兵士は身を乗り出し、固い髭が生える顎を肉付きのいい拳に乗せた。
「一人旅か? 勇敢なこった」
「ただのバカかも」
他の兵士が口を挟む。
「うむ、ただのバカかもな」
髭の男が同意した。
「エミエル・レジス。あんた道に迷ったのか? ならツイてるぞ、丘の奥を通っていく道があるからな。そこをまっすぐ進むだけだ」
「分かっている」
「ならどうしてここに来たんだ?」
「お前たちが追い出した集落の住民と会った。子供まで住み家から追い出したと聞いている」
レジスは後ろ手にドアを閉じて、テーブルに歩み寄る。何人かの兵士が剣に手を伸ばすのが見える。
「命令どおりにしたまでだ」
髭男が返答する。レジスは彼と目を合わせて手を掲げた。すると卓上に並んだ瓶が震えだした。
「命令は変わった。この場所はお前たちのものではない。すぐにヴィドルトに向かえ。私と会ったことも、ここにいたことも忘れろ」
レジスが低い声で告げると、髭男の顔は緩み、表情を失った。
「はい、我が主よ」
小屋から最後の兵士が出ていくのを見届けたレジスは、目が霞むのを感じた。ベンチに近づこうとするが、脚がうまく動かない。彼は倒れ込み、椅子に強かに頭を打ち付けた。
意識を手放しながら、レジスは旅の始まりを思い出していた。荒れ地の病院。そこで聞いていた、死にゆく者たちのうめき声。死の匂い。
「彼らはどうせ死ぬ」
「私は殺さない」
デトラフがそばにいる。手から赤いものを滴らせながら。
「レジス、お前には血が必要だ。」
「金はどこだ!? 吐け!」
「ううう!」
そんな2人のやり取りを、カラスたちが無感情に眺めている。兵士長は溺死体のように青ざめた顔をしていたが、オシアンに喉元を掴まれると一気に顔を赤らめた。
「ううう!」
そこにアースキンが割って入った。彼は悪態をこぼし、抱えていた枝の束を地面に落とす。そして大股でそりまで近づき、オシアンのコートを掴んで彼を投げ飛ばした。
老人は顔を真っ赤にし、毛皮の下で空気を求めてあがいていた。
「殺す気か、この間抜け!」アースキンは怒鳴り、相棒のあばらに蹴りを食らわせた。
「何を考えてる? 奴が起きたならなぜ俺を呼ばない?」
オシアンは肘を使って這い進み、アースキンの蹴りから逃れようとする。
「ちょっと脅しつけてやろうと思っただけさ」と語る顔に、下劣な笑みが浮かんだ。
アースキンは彼を睨みつける。もしオシアンが隠し場所を聞き出せていたら、相棒のことなど置き去りにして、兵士長を連れて躊躇なくこの場から逃げ去っていたことだろう。彼らがネリスを見捨てたように。
「また同じことをしたらタマを吊るし上げてやる」
「2人とも吊られるさ」と兵士長が吐き捨てた。「脱走兵どもが。裏切り者め!」
すると2人は笑い声をあげた。
「そんな言い方はないだろ、司令官殿。俺たちは死にかけのあんたを救い出してやったんだぞ? 病気の世話もしてやった。少しぐらい感謝してほしいもんだな」
「感謝の印に処刑人の斧でも食らえばいい」
アースキンは荒く強張った手に息を吹きかけ、そりの手すりに寄りかかった。起き上がったオシアンもその反対側に立つ。白くなった眉毛の下で、兵士長の目が彼らを睨みつけた。賽は投げられている。オシアンが本性を晒した以上、もはや嘘をつく意味はない。
「じいさん、戦利品をどこに隠した?」
「あれは部隊のものだ。皆で公平に分ける」
「笑わせんな。ディリンゲンでの略奪品だろう。ああ、盗人にも仁義ってやつか?」
「征服者の法のもとで奪ったに過ぎない。ニルフガードから取り返した街でな。そんなことも分からんのか、アースキン。戦争は初めてか?」
「いいや。だが最後にはなるかもな。お宝さえ手に入れば。トランペットの後ろで行進するのはもうご免だ」
オシアンは口を引き結び、ナイフを取り出した。刃につばを吐き、袖口でそれをふき取る。
「言い訳を聞いても時間の無駄だ。さっさと切り刻んで歌声を聞かせてもらおう」
アースキンはただ肩をすくめ、暗黙の了解を示す。わずかだが、彼にはまだ兵士長に対する敬意が残っていた。兵士長は鋼の意志によって、幾度となく部隊を勝利に導いたのだ。そんな彼を病気の動物のように連れ回すのは気が引けた。だから彼は時間を与え、兵士長自身に状況の深刻さを理解させた。
当然、オシアンはそんな事情は知らない。彼がフォルテスト王の軍に加わったのは昨秋で、父親の農場がケイドウェン軍の騎兵隊に略奪された後のことだった。その経験からオシアンは学んだのだ。「兵士」とは、「合法的な盗人」だと。だからこそ彼は軍に入隊した。
刃が毛皮の下に滑り込み、冷たい切っ先が兵士長の肌に押し当てられた。傷のついたその顔に、怒りや苦々しさを上回る無力感が浮かんだ。己の運命を受け入れ、彼は語る。
「ヤルーガ河だ。ディリンゲンから馬車で東へ1日のところに製材所がある。そこでニルフガード軍と戦闘になったんだ。連中は荷船で向こう岸まで撤退するつもりだった…」
アースキンとオシアンは負傷した兵士長の上にかがみ込んだ。飢えたハゲワシのように。
デトラフはレジスをテーブルにつかせた。周囲を見回し、地下室への落とし戸へ向かう。
「無茶をしたな」と彼は言った。
「ああ」
「また“時間があればいい”などと言うなよ。すべきことは分かっているはずだ」
「ああ」
暖炉の火は消え、捨て去られた小屋は闇に包まれている。ネリスはテーブルにつき、マンドラゴラの自家製酒を飲んだ。レジスは手をこめかみに当て、ぶつけた箇所を揉んでいる。
「助けが要ると言っていたな」
「ええ」
「条件が1つある。もう隠しごとはなしだ。真実を話してくれ。全てを、できる限り簡潔に」
「真実なんてつまらないもんよ、レジス」彼女は溜め息をついた。「ディリンゲンの近くのどこかに、戦利品の入った箱がある。アルノーが… それが兵士長の名よ… 彼が隠したの。戦争終結まで安全に保管しておくためにね。ところがいざ戦いが終わってみると、兵士長は戦場で負傷してしまっていた。野戦病院で惨めに死なせるわけにはいかない。だから私たちは彼を連れ出した」
「戦利品のありかを聞き出すために、か」
ネリスは口をつぐんだ。レジスは両手を広げて言う。
「悪いがそれだけでは信用できないな」
「後を追わないと兵士長がどうなるかは分かるでしょ? アースキンとオシアン… あの2人がどんな奴らか、あんたも見たはずよ」
「お前は違うと?」
「私は金が欲しいだけ。彼には死んでほしくない」
「それは気高いことだ」
「気高いのはあんたよ、レジス。否定しないで。何日もアルノーの世話をするあんたを見た。そんな必要はないのに、私のことも助けてくれた。真実を知りたいなら教えてあげる。あんたは既に分かっていた。私たちが助けに向かわないと、兵士長は死ぬってね。だからあんたは私について来る。やむにやまれぬ良心が彼を見殺しにできないから」
デトラフが床の落とし戸を持ち上げて言う。
「彼女の言うとおりだ、レジス。片をつけようじゃないか」
*
地下室は湿っぽく、さらに深い闇に包まれていた。
レジスは木炭で床に線を引き、紋様を閉じる。その円の内側に、フェン・カーンの小屋から持って来た粘土製の椀を置いた。
「デトラフ、なぜあの男を助けた?」
「あの男?」
「アイナ川のテメリア兵だ。放っておくこともできた」
「ああ。だがきっと… お前なら見捨てないだろうと思った」
古代の魔法陣が発光し、空気がざわめき出した。デトラフが椀の前に立つ。素早い動きで手首を切り、血が流れ落ちる。
「これまではずっと楽だった」と彼は告げる。「ずいぶんと長く生きてきて、人間や彼らの文明もどきについては確固たる考えを持っていた。人間は疫病のように世界各地に広がり、機能しようのない滅茶苦茶な文明を築いている」
「だが、考えを改めたか」
「いや、そんなことはない」
「だが何かが変わった」
デトラフは顔を歪め、感覚のなくなった指を小刻みに動かした。
「お前は私より人間に価値を見出している。性懲りもなく人間を助けようとするのは…」
「愚かに思える?」
「興味深い」
デトラフは傷を閉じて魔法陣を離れた。入れ替わってレジスが円に入る。彼は両手で椀を掴み、呪文を囁くとその中身を飲んだ。
新鮮な血が彼の内側に流れ込み、高揚に体が打ち震える。消えていた吸血鬼の感覚が一気に目覚めた。あらゆる囁き声や、雪を舞わせるつむじ風の音が彼の耳に届く。ヤルーガ河の濁った水のざわめき。馬のいななきと、遠い道を駆ける足音も。
*
馬がうなり声をあげた。その体にソレンセンの手綱が叩きつけられる。彼は小屋から十分な距離を取りたかったのだ。
トゥーロッホ高地の空き地へたどり着いた頃には夜明けが訪れていた。松の木が辺りの岩に長い影を落としている。彼は倒木に腰かけ、クロークに身を包んだ。
「サブリナ」
「今が何時だか分かってる? 女魔術師は眠らないとでも思ったの?」
「吸血鬼を見つけたぞ」
溜め息がもれる。
「片づいたの?」
「いや。だが奴らの会話を聞いて、誰を追ってるのかが分かった」
「ねえ、ソレンセン… 尾行を頼みたいならその専門家を雇う。あなたは確かウィッチャーよね?」
「ああ、ウィッチャーだ。そして間抜けでもない。灰色の髪をしたレジスだが… 奴を殺してやれば人助けになると思ったが、そう簡単には死んでくれそうにない。ヤルーガ河で兵士の一団を手駒にしたようだ」
「また報酬額を上げろって言うの?」
「助けがほしい」
軽い笑い声がした。
「それならちょうど準備ができてる」
閃光が瞬き、すぐそばに〈門〉が現れた。渦巻く混沌の向こうから力が注ぎ込まれ、武器の形が浮かび上がる。その輪郭は次第に明瞭になり、熱で満たされるとついに固形化した。そうして雪の上に落ちたのは、装飾の施された短剣だった。
ソレンセンは短剣を拾い上げ、ルーンに指を這わせる。
「これでどうしろと? 杭でも削るか?」
「魔法をかけてあるの。吸血鬼の肌に触れると発動する仕組みよ。呪文を完全に再現できたわけじゃないけど、その短剣に込めた魔力で十分なはず」
「本当に効くのか?」
「分からない。でもその呪文を生み出したヴィルジフォルツは恐ろしく賢い奴だった。呪文の再現は高くつく挑戦だったし、剣に込める作業だけで1週間もかかった。だから上手く使うのよ。効果は1度しか発動しない」
「吸血鬼は2人いると言ったはずだが」
「ええ、分かってる。でもあなたは…」
ソレンセンは溜め息をついた。倒木から跳び下り、短剣をベルトの下にしまい込む。
「でも俺はウィッチャーだ」
「あなたなら上手い手を考えだせる」彼女はそこで間を取る。「そうでしょ?」
ソレンセンは馬に乗り、西へと伸びるそりの跡を見つめた。
「選択肢があるのか?」
蝶番ひとつでかろうじて引っかかっていたドアが壁に激しく叩きつけられた。オシアンが製材所から勢いよく飛び出してきたのだ。
「何もない。何も! 錆びたコイン一枚落ちてない!」
「あいつが言ってた、崩れかけのレンガはあったのか?」
「地下室のレンガの半分は崩れかけだ! ほとんど壁から外してみたが、何かを隠せる場所なんてなかったし、むしろ外から土がなだれ込んできてた。絶対にここじゃない。断言できる」アースキンは広場を見渡した。掘り起こされた集団墓地のあちこちには野生動物の餌になった、凍りついた死体が散らばっている。死体が身にまとっているのは蠍の紋章で装飾された黒いニルフガードのクロークだ。
「間違いない。こいつらはディアラン第七旅団の槍兵だ。爺さんの言ってたとおりだ」
「奴がボケてたってことか? さっさと起こせ」
そりの方からケタケタと笑い声があがった。兵士長はいつの間にか目を覚まし2人の会話を聞いていた。彼は困惑する2人が面白くてしかたない様子で笑っている。
オシアンは「何がおかしい?」と唸り、老人に拳を振り上げる。アースキンは慌てて彼の手首を掴んだ。
「落ち着け。なにか話そうとしてる」
アースキンは司令官の口元に耳を寄せ、しわがれた囁き声に耳を傾けた。「バカどもが、貴様らはもう終わりだ」
兵士長はニタニタ笑いながら体に巻きつけた毛皮の中から手を出し、震える指先でディリンゲンを指し示した。葉を失ったトネリコの森の奥から傾いた太陽が差し込み、大地に不吉な長い影を落としている。2人の脱走兵は老人が示した方向を見渡した。
アースキンは何かに気づいたように、突然しゃがみ込み近くの死体を調べた。鎧の鉄板は交差する爪痕によって引き裂かれており、中の凍りついた肉が露出している。骨は狼のものよりもずっと大きな顎に噛み砕かれているようだ。
テメリア兵は慌てて立ち上がり相棒に向き直る。その顔色は周囲に転がる死体と同じ蒼白だった。
「死人食いだ」
恐ろしいギラついた目が、夕暮れ時の木々の合間で光っている。兵士長の邪悪な笑い声が2人の耳について離れない。
*
ウィッチャーはそりの跡を追っていた。森が開け、倒木のそばに建つ放棄された木こり小屋にたどり着く頃には夕暮れ時だった。突如、腹をすかせた咆哮が穏やかな川のせせらぎをつんざく。馬は鼻を鳴らし、首を振り、先に進むのを拒む。その場に置いて徒歩で進むしかなくなった。
ソレンセンは並ぶ木々の影から広場に出た。満月が、ヤルーガ河の水面、積もった雪、そしてウィッチャーの剣を銀色に輝かせた。グールの群が製材所の周りを忍び足で歩き回っている。中に立てこもっている人間を狙っているのだ。水車の近くに、乗り捨てられたそりが見える。その上に寝かされた人物が1匹のグールに食われていた。肉が引き裂かれ、骨が砕ける嫌な音が響き渡っている。
弩の一撃で、そりの上の怪物を近くの木に縫い付ける。
ソレンセンはベルトのフックから小さな爆弾を外し、イグニで導火線に火を点けて“仕事”を始めた。
*
ウィッチャーの姿は化け物たちと負けず劣らず恐ろしいものだった。
爬虫類を思わせる目。首とこめかみを走る黒く膨れ上がった血管。モンスターの血に染まり異臭を放つ衣服…
「酒はあるか?」
不思議なもので、その一言だけで恐ろしいウィッチャーがずいぶん身近に感じられた。オシアンは彼に水筒を差し出す。
「お前たちの仲間がこっちに向かっている。まもなく合流するだろう」
脱走兵はちらりと目を見合わせた。アースキンは本能的に剣の柄に手を添えたが、勝ち目が薄いことは悟っていた。
「どうして俺らに仲間がいると思ったんだ? あんた、尾行してたのか?」
「俺の目当ては途中でお前たち一行に加わった2人だけだ」
「何か因縁でもあるのか?」
「あるといえばある。奴らの討伐を依頼された。もう気づいているかと思うが、俺はウィッチャーでね」
「へえ、あいつらドラウナーか何かだったのか?」
「吸血鬼だ」
ウィッチャーの答えを聞いたアースキンはしばし言葉を失った。
「そうは見えなかったが」
なんとかそう絞り出した彼に、ウィッチャーは自分も驚いたと肩をすくめ、彼らが非常に危険な存在だと話した。
さきほどの失望から抜け出せずにいたオシアンは、錆びついた工具の山を責めるかのように蹴飛ばした。蹴られた工具は、物悲しげな音を立てて壊れる。
「ジジイにだまされた。あいつは俺らが死ぬだろうと思ってここに誘導した。こんなに遠くまで来たのに1オレンも儲からないなんて」
ウィッチャーはポーチの中に手を差し込んだ。血で汚れた指先で、取り出したコインをもてあそぶ。表がスフィンクス。裏が戦車。月光がその古い金貨に反射し、脱走兵たちは魅入られたかのように輝く硬貨を呆然と見つめた。
「お前たちの目的は知らないが、もっと割のいい仕事ならあるぞ。こっちには人手が必要なんでね」
オシアンは生唾を飲み込む。「あんた… 金貨をくれるのか?」
「払うのは俺じゃない」ウィッチャーは悪意に満ちた笑みで顔を歪めた。「吸血鬼どもだ。連中はたっぷり貯め込んでる。お前たちには… 罠を仕掛ける手伝いをしてもらいたい」
戦場は静寂に包まれていた。満月の光が、製材所から垂れるつららや、兵士の死体の錆びかけた鎧にきらめいている。
一行は水車の近くでそりを発見した。
レジスは死骸となった血まみれの雌馬をまたぎ、兵士長を覆っていた毛皮をどかした。
目のあるべき場所には黒い穴が穿たれ、頬は切り刻まれ、口は苦痛の叫びをあげた形で固まっている。
ネリスが身をかがめて嘔吐した。
そんな彼らの背後、影に包まれた茂みの奥でボルトリングがカチッと音を立てた。
暗闇を閃光が駆け抜ける。発射された矢はレジスの腕を砕き、そりに釘付けにした。傷口が煙をあげ、肉の焼ける臭いが辺りに充満する。
「そこ!」とネリスが叫ぶ。彼女は鞘から剣を抜き、木々のほうへと駆け出した。
デトラフには襲撃者の正体が既に分かっていた。あの時の音を、銀の表面に浮かぶルーンの輝きを忘れてはいない。
彼は瞬時に姿を変え、革のような翼を広げて森の方角へ飛び立つ。そのままネリスを追い越すと、ウィッチャーと対峙するべく先ほどの茂みに降下していった。
*
怪物は餌に喰いついた。
ソレンセンは彼が飛び立ち、翼を広げ森の中へと消えていく様子を見ていた。傭兵が剣を抜き、その後を追っている。
ウィッチャーはこの判断に感謝していた。彼女のことは殺したくないと思っていたからだ。
彼は霊薬を飲み、大きな溜め息をつくと隠れていた板の山から飛び出した。大股で2歩進み、そりに釘付けとなったままの吸血鬼に詰め寄った。素早い一撃で首を断ちにかかる。
銀の刃が振られ、風を切る音がする。
だが一拍遅かった。
吸血鬼は寸前で腕を外し、その爪で剣を弾いていた。それでもウィッチャーは止まらない。彼は剣を振り下ろすと見せかけて足さばきのリズムを崩し、胴体の中心めがけて鋭い突きを繰り出した。
怪物は後ずさってそれをかわし、ウィッチャーに殴りかかる。だがこちらも外れ、きらめく爪がソレンセンの頭のすぐそばの空を切る。続いてウィッチャーが片膝をつき、低い位置を斬りつけた。これが命中し、怪物は下腿に傷を負う。そしてそのまま、一瞬の迷いもなく首への追撃を狙う。吸血鬼は手でその攻撃を防ごうとする。刃が指を貫き、勢いを失い、口をかすめる。
怪物がウィッチャーに突進し、喉元を掴んだ。ソレンセンはうめき声をあげ、ベルトから爆弾を掴み取って足元に放った。爆発が起こり、甲高い悲鳴が後に続いた。煙が辺りを包み込み、一寸先さえ見えなくなる。ウィッチャーは剣を振り、怪物の胸元を斬りつけた。さらにアードの印で後方へ吹き飛ばす。吸血鬼の体はそりに打ちつけられ、兵士長の死体と共に闇の向こうへ消えていった。
ソレンセンは首をなでながら激しく息を吸った。その唇には笑みが浮かんでいる。怪物は大量に出血していた。マンティコアの銀でつけられた傷がすぐにでも燃え上がり、さらに体力を奪ってくれるはずだ。
ウィッチャーは両手で剣を握り締め、呼吸を整える。
「片をつける時だ」と彼は言った。
*
デトラフの視界に人間の輪郭が赤く浮かび上がった。石弓を持った1人と… 影にもう1人潜んでいる。彼らの血からは嗅ぎ覚えのある匂いがした。少し前まで旅を共にした愚かな2人に違いない。だがウィッチャーの存在を感じなかった。どうも気がかりだ。
そこで弦を弾く音がした。しかし矢が命中することはなく、爪の一振りによって弾き飛ばされる。デトラフは急降下し、翼で捕えて襲撃者を枝から突き落とした。男は落下しながら武器を手放し、雪の吹きだまりに激しく体を打ちつけた。
デトラフは鋭い弧を描いて飛び、それから着地すると人間の姿に戻った。もう1人は身を隠せているつもりだったのだろう。男が木の陰から飛び出し、吸血鬼の首に短剣を突き立てようとしてきた。だがデトラフは圧倒的な速さで奇襲者の手首を掴んだ。彼の視線が刃に留まる。そこに刻み込まれたルーンが青く不吉な光を放っていた。僅かのあいだ興味をひかれたがすぐに男へと注意を戻し、その手に掴んでいた骨を砕く。奇襲者がうなり声をあげ、力を失った手から武器が落ちる。デトラフは男を雪の中に放り込んだ。
彼は縮こまっている2人の男を睨みつける。恐れおののくその姿は、刑の宣告を待つ罪人のようだ。彼らの心臓はハンマーのように激しく鼓動を打っている。肺を大きく膨らませ、極度の緊張のなかで息を吸う。吐き出された息が、冷気の中で白くうねった。恐怖に震え、苦悶と欺瞞に満ちている――いったい何のためだ? どんな意味があった?
「なぜだ?」と彼はたずねた。その息は冷たく、目に見えない。
2人が強張った喉を動かし、歯の震えを抑えられるよりも先に、製材所の方向からネリスが現れた。
「バケモンだ」オシアンは声を絞りだし、折れた腕をぎゅっと掴む。「お前、奴らと一緒にいたんだろ? こいつらはバケモンだ!」
ネリスは返事をしなかった。オシアンのぎらついた視線が、地面に落ちた短剣に向けられている。それに気づいた彼女は剣を拾い上げ、デトラフのほうを向いた。
「兵士長はこいつらに殺された。とどめを刺して。やらないなら私がやる」
吸血鬼は手振りで彼女を制す。
「分からない。なぜだ?」と彼は繰り返した。「兵士長の情報でここまでたどり着いたんだろう? ならばなぜ、金を奪ってさっさと立ち去らなかった。なぜ我々を襲った?」
「金なんてなかったんだよ!」オシアンが叫んだ。「あのジジイは、死人食いがのさばる戦場までわざと俺たちを誘い込んだ! 秘密は墓に持ってっちまったのさ。小賢しいネズミ野郎め!」
「だがこいつらは」とアースキンがデトラフを指さす。「とんでもない財宝を持ってやがるんだ! 古代の墓の金貨さ。馬を買った時に使ったのもそれだ。ウィッチャーが… ウィッチャーが教えてくれた」
金属が瞬いた。ネリスは投げられたコインを掴み、それをよく観察する。確かに価値のあるものに違いない。
「そんなのを大量に持ってんのさ。使い切れないほどにな。俺たちが必死こいて兵士長のお宝を追ってたってのに…」
デトラフは失望していた。レジスの話を聞き、人間にもう少し期待してみようと思いかけていたからだ。彼らは欲望に呑まれ、衝動のままに行動するだけの不誠実な存在ではない。品位にかけた卑劣な存在だという印象は誤りなのだ、と。しかし彼の友人は間違っていた。人間は救いようのない存在だ。兵士長が隠した財宝と同じように、人間の中に価値あるものなど見つからなかった。宝の箱は空っぽで――それはこの先も変わるまい。
デトラフはのたうつオシアンを片手で掴み上げ、首をかしげて牙を伸ばした。血の香りが彼の鼻を満たす。高揚感が体中を駆けめぐる。
だが突然、痛みに襲われた。
ネリスが毒蛇のごとき素早さで短剣を振りかざし、デトラフの腕に深く突き刺したのだ。吸血鬼はオシアンを離して後ろに跳び退いた。鋭く息を漏らし、歯をむき出しにする。魔力の刃を刺された場所から青い炎があがった。炎はゆっくりと彼の腕を呑み込み、首にまで迫ろうとする。邪悪な魔法から逃れるため、彼は武器に手を伸ばす。そこですかさず、アースキンが雪の中から石弓を掴み取った。素早く狙いをつけ、矢を放つ。銀の矢が空気を切り裂き、吸血鬼の腕を木の幹に打ちつけた。
片方の腕を釘付けにされ、もう片方の腕が魔力の火で焼かれていく。デトラフは血の力を求めて変身を試みるが、ウィッチャーの銀がそれを阻んでいた。
彼はおぞましい咆哮をあげた。夜がその声に応え、どこかから遠吠えが聞こえる。
「私の分け前は2倍にしてよ」オシアンを起こしながら、ネリスが告げた。
レジスは立ち上がろうとした。だが骨の折れた脚は言うことを聞いてくれない。胸の傷からは血が滲み、指を失った手は絶えず痛んだ。
レジスはかたわらの兵士長を羨ましげに見つめた。この男はもう何も感じずに済むのだ。
そこへウィッチャーが近づいて来る。銀の刃に月明りがきらめいていた。
こうするしかないんだ。
許してくれ。
彼は死体に這いより、その肌に牙を突き立てた。
舌に残る鉄のような後味。激しい高揚感が波のように押し寄せ、体の内側で脈打つ。傷は癒え、痛みは和らぎどこかへ消え去った。
壊れたそりの陰からウィッチャーが現れ、悪態をつく。レジスは立ち上がり、大きく息を吸い込んだ。その目が赤く染まる。
彼は獰猛な獣のように咆哮をあげた。その顔は不吉な相貌へと変化し、指の残っている手から長い爪が生え出てくる。
そこから先は曖昧だった。全てがベールを一枚隔てたように遠く見え、自分の体が自分の体でなくなったような、原始的な獣の肉を被ったような感覚だ。
そして獣は血を求めている。
ウィッチャーは指を折って印を作った。だが今回は易々とかわされ、放たれたエネルギーは雪を吹き飛ばしただけだった。さらに爆弾へ手を伸ばすも間に合わない。まるで速さが違う。吸血鬼は強烈な一撃を浴びせ、ウィッチャーの体はかぎ爪に貫かれた。指の力が抜け、銀の剣が血に染まった雪に落ちる。
獣は牙を伸ばした。
動脈がうずき、心臓が高鳴り、血がたぎっている。もはや衝動を抑えることはできない。本能に従うしかないのだ。
それでも屈したくはない。
レジスはそこで固まった。顔つきが柔らかくなり、シュッと音を立てて爪が縮められる。ウィッチャーの体は解放され、雪の上に崩れ落ちた。
辺りは夜明け前の静けさに包まれている。血管の脈動は弱まり、やがて完全に鎮まった。彼はウィッチャーの上にかがみこみ、その目をじっと見つめる。
「私は怪物ではない」と彼は言った。
それから踵を返し、ウィッチャーを残して木々の向こうへと去っていった。
*
青い炎はデトラフの手から前腕にかけてを焼き焦がし、肩と首に広がっていた。
「ウィッチャーはこれで殺せると言ってたぞ。骨まで焼き尽くすってな」
「何度もだまされてたまるか! おい、金を出せ」オシアンはゆっくりと告げた。
吸血鬼は無事だったほうの手の、感覚のなくなった指を小さく動かした。腕を貫いている矢はわずかに緩んでいる。彼はクロークを押し下げ、ベルトの小袋を外して地面に投げた。
傷を負いながらも、真っ先に手を伸ばしたのはオシアンだった。だがそこで石弓のきしむ音がする。矢が装填されたのだ。
「そいつに手を出すな」アースキンが低い声で告げる。「お宝を奪いに来たってのに、お前はまるで役に立たなかったよな。この野良犬め」
「手伝ったろ!」
「何を偉そうに。ネリスは奴を刺したぞ」
「それだけ分け前を多くしてもらわないとね」と彼女は言った。
「するかよ」アースキンは横目でネリスを睨みつける。「ついさっきまで吸血鬼と組んでた奴が。オシアン、動くなよ。動いたら矢を撃ち込む」
「よせ… こっちは2人だぞ… 再装填は… 間に合わない…」
「さっさと撃ちな、アースキン。それから逃げよう。早くしないとウィッチャーが戻ってきて分け前を要求される」
アースキンは鼻で笑った。「蛇みたいに狡猾な奴だ」
「3人より2人で分けるほうがいいでしょ?」
「ウィッチャーを敵に回していいのか?」
「2人いれば対処できる」
「冗談だろ。お前を信用する気はない」
彼らが言い争っている隙をつき、オシアンは木々の向こうへ逃げ始めた。が、すぐに2人に追いつかれる。ネリスは足を引っかけて彼を転ばせた。オシアンが凍った地面を転げてくぼみに落ちると、2人は口論を再開した。
それから間もなくして、木々の合間に目が浮かび上がる。デトラフの呼び声に応じ、大挙してやって来たそれらは、そう遠くないトネリコの木を取り囲んでいるが、音もなく現れたそれらに脱走兵たちは気づいていない。それらはじっと命令を待ち、その口から熱い唾液をしたたらせた。
そのうちの1匹が歯を使って矢を引き抜き、デトラフを木から解放する。彼は自由になった手の指を伸ばし、固くなったそれらをほぐした。魔力の火に焼かれた腕を不快な音と共に噛みちぎり、刺さった短剣ごと地面に放る。その熱がジリジリと雪を溶かしていく。
彼は手を上げた。夜の生き物たちは期待に震えている。兵士長はあの人間たちの本性を誰よりもよく理解していたようだ――彼らがどんな報いに値するかを。だからデトラフは兵士長に敬意を払うことにした。
彼は死人食いを解き放った。
*
夜明けには雪が降っていた。
デトラフはトネリコの老木のそばに腰掛けている。そこにレジスがやって来て、彼の隣にひざをついた。彼らは無言のまま、白い毛布の下へ消えていく3人の死体を見つめた。彼らの間には金貨が散らばっている。
「あの2人は… 相応の報いを受けるべき行いをした」とレジスは言う。「だがこんな運命を迎えるとはな」
「3人ともさ。それぞれが自ら招いたことだ。その本性が破滅を呼んだ」
「すいぶん人間に詳しくなったな。すっかり専門家だ」
「専門家? まさか。だが奴らの真実はよく分かった」
デトラフはレジスの負傷した手を見てたずねる。
「ウィッチャーは?」
「逃がした」
「どうかしてるな」
「いいや。私はお前が思ってるような奴じゃない。それだけのことだ」
木々の隙間から日の光が差し込み始めた。冷たい風が葉のない枝から雪をさらっていく。レジスは立ち上がって荷物を整えた。
「私はもう行く」
デトラフは生気の抜けたネリスの目を見つめた。手を伸ばし、その指の間から金貨を摘まみ上げる。
「行けよ」と彼は告げた。「人間に紛れて暮らすといい。お仲間と共にな。それが命取りにならないことを祈ろう」
「お前はどうするんだ?」
デトラフは金貨を袋にしまい込んだ。
「まだ分からない。だが最初に行く場所は決まっている」
*
ザッ、ザッ、ザッ、パシャッ。
「サブリナ」
彼は次の小石を拾い上げた。平らで滑らかな表面。完璧だ。ヤルーガ河の穏やかな水面が、日の光にきらめいている。
ザッ、ザッ、ザッ、ザッ、パシャッ。
「片づいたの?」ゼノヴォクスの向こうから彼女の声がする。
「ある意味な。この件からは降りさせてもらう」
そこで沈黙が続いた――ひどい嵐の前触れを思わせる静けさだ。
「降りるって、一体どういうこと?」彼女の言葉にはサソリの一刺しよりも猛烈な毒が含まれていた。
「そのままの意味だ」ソレンセンは手の中で石をひっくり返し、手のひらで重みを計ると水面に向かって水平に投げつけた。ザッ、ザッ、パシャ。
「怖気づいたわけ? 本性が露わになったわね、この臆病者。とんだ半人前。あんたなんて無価値なクズよ…」
悪態は延々と続いた。サブリナは饒舌に語り、驚くほど豊かで下劣な想像力を発揮した。その叫び声でゼノヴォクスが振動していたほどだ。
ソレンセンは水面を見つめながらそれを聞いていたが、やがて愛想をつかした。彼は魔法の箱を拾い上げ、手のひらで重さを計る。
パシャッ。
*
暖炉の火の中で薪が割れた。心地よい暖かさが部屋中に広がっていく。
エインは毛皮の上に座って弓を引いた。フィドルの音がどうもおかしい。彼女はピンを回して調律を行う。だが演奏を始めるより先に誰かが扉を開けた。
彼女はその男を知っていた。
「お父さんはどこだ?」
「カゲンよ。今日は… ひとりなの?」
「ああ、そうだ」
「どうぞ。中で暖まって」
来客はテーブルについた。彼は炎を見つめ、何か考え込んでいる。
「ルドカはちゃんと役に立った?」
「彼女は旅立ってしまったよ」
エインは楽器を下ろし、薪を動かした。来客がベルトに手を伸ばす。
「金貨を受け取っただろう… あれはものすごく価値のあるものなんだ」
「金貨はもうないよ」
「分かってる」
来客は小銭入れを開けて2枚のコインをテーブルに置いた。エインが溜め息をつく。
「ダメよ、そんなの。ルドカの分はきちんと払ったじゃない。金貨がなくなったのは私のせいだもの」
来客は長いあいだ沈黙した。
「こう考えてくれ。これは正当な対価なのだと」
「なんの?」
「今こうして、私に教訓を与えてくれた分だ」
彼は立ち上がって出て行った。エインは輝く金貨を見つめていた。少し経って、彼女は羊のなめし皮のコートを手に夜の中へ駆け出した。
雪についた足跡は数歩進むと消えていた。男の姿はどこにも見当たらない。
冷たい風が寂しげな木々の間を吹き抜けるばかりだった。長い冬の前触れだ。